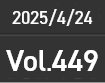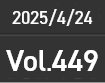出版社名を見て、「え? アマゾン?」と驚く人もいるかもしれません。そう、本書はいわゆるアマゾンのセルフ出版本なのです。キンドル版は電子書籍なので在庫なし、紙版もアマゾンのオンデマンド印刷なのでこちらも在庫なし。とてもリーズナブルに自費出版で本が出せるシステムです。
しかしセルフ出版にありがちなチープさが本書にはありません。表紙もプロの手によるイラストが入っていますし、レイアウトデザインも出版社が作る本と遜色がありません。
そのあたりの経緯が知りたいと、著者のnoteを読んでみました。
https://note.com/takurami/n/ncf3d1ac823dc
どうやら、原稿を書き始める段階から、大手出版社出身の出版コンサルタントに力を借りたようです。このコンサルタントはキンドル出版に特化したコンサルティングを行っているそうで、この人が原稿執筆から表紙デザインの作成、キンドル出版におけるさまざまなテクニックをサポートしてくれたということです。
これまで出版といえば、出版社所属の編集者がマンツーマンで著者に寄り添い、本の完成までをサポートするのが普通でした。その場合、出版のプロセスは出版社主体となります。
しかし本書の場合は、あくまでも著者が出版の主体で、キンドル出版を熟知したプロがサポートするというスタイルを取っています。これから日本の出版界にもそういう形が普及していく予感がします。
ユニークなのは著者が本のマーケティングを取り仕切っていることで、電子版、紙版それぞれの価格設定やキャンペーン価格の決定、ランキング上位に表示されるためのカテゴリー選びなど、普通は著者が関与することのない部分にまで著者の意思が反映されています。
このnoteには編集者による著者インタビュー動画もあるので、キンドル出版に興味のある人はぜひご覧ください。
それでは、本書の目次を紹介しましょう。
・はじめに
・序章 私の倒産体験 目一杯働いていたのになぜ倒産したのか!?
クイズ:あなたなら、どちらをやりますか?
9割の人が勘違いしている「効率のいい方法」
・第1章 なぜ「大きくまとめる」が蔓延するのか?
世の中は大きくまとめたがる
身近なところにある「大きくまとめたがる」
仕事の現場で起こる「大きくまとめたがる」
まとめたがる理由はズバリこれ
本当に「効率的」であるとは?
本来の目的は何か?
大きくまとめないと「不安だ」「怖い」という感情が起こる
・第2章 今からできる身近な「小さく分ける」
渋滞を起こすボトルネックはどこか?
ボトルネックが成果を決める
ボトルネックを意識して4倍のスピードアップに
今から試せる「飲食店オーダーの通し方」
まとめて注文することで起きること
お店もお客もハッピーな注文方法とは?
家事時間30%短縮・家計が月2万円浮いた!
週1回の大量買い出しをやめてみたら……
小さく分けることの真の威力
トヨタの「待ち時間」はどれくらいある?
「待ち時間」を減らして業績アップした事例
「待ち時間」に注目すると劇的な改善が可能に
・第3章 なぜ、「小さく分ける」と事業が儲かるのか?
意外なところに詰まり? 歯医者さんの劇的な業務改善
「小さく分ける」ことで一石三鳥に
「私がボトルネックです!」~ある社長の勇気ある宣言~
パワフルな社長が、なぜボトルネックに?
「仕事の詰まり」はシンプルに解消できる
製造業の常識の「手を止めるな!」は思い込み
常識を覆す「ロットを小さくする」効果は?
さらに常識外れの「値上げ」提案
これからの時代に大量生産は合っていない
コロナ禍でも「小さく分ける」で大変革した老舗石鹸工場
新工場を建設したのに生産が上がらないのはなぜだ?
目標を考えるときも「小さく分ける」
製造工程を「小さく分ける」と、詰まりが見えた!
営業の仕事も「小さく分ける」ができる
3つの「小さく分ける」が大きな成果に
有名日本酒メーカーは徹底的に小さく分けている
12階建てのビルで1年中酒造りが可能に
小さなタンク300本がもたらすメリット
・第4章 「小さく分ける」と起こる抵抗感に対処する
人は6回抵抗する
小さく分けると不安!に対処する
不安という感情が大きくなっている
不安と向き合うシンプルな方法
売れ残り廃棄が課題のケーキ屋さんはどうしたか
不安と向き合うときの2つのポイント
小さく分けると高くつく!障害を乗り越える
みかんで考えるまとめ買いの真実
アパレルにはまとめ買いの罠がいっぱい
革新的なシャツメーカーが行った小ロット生産
ビールが教えてくれた教訓
全体を見渡す広い視野の重要性
おまけ:障害を小さく分ける実践例
「何か嫌だ」未知への恐怖を乗り越える
疑似体験で不安や恐怖を自信に変える
「嫌だな」という感情のメッセージを受け取る
・第5章 「小さく分ける」ための5つの法則
小さく分けるがうまくいく5つの法則
事例に見る5つの法則の組み合わせ
・第6章 「小さく分ける」で創れる未来
「小さく分ける」は地域を創り、世界を再生する
会社が倒産したことで得られた気づき
「小さく分ける」の大きな可能性
台風被災対応を大きく改善した市役所さん
「小さく分ける」で見直したこと
5つの法則での分析:すべてを組み合わせた泉大津市役所の災害対応
震災から考えた「小さく分ければ世界が持続可能になる」
もし、私たちが「小さく分ける」を実践していたら
「小さく分ける」で持続可能な未来へ
・おわりに
・参考文献・資料等
・著者プロフィール
まず、最後の著者プロフィールから見てみましょう。
著者である森本繁生氏は、中小企業の組織成長ファシリテーターでTOC(制約条件の理論)コンサルタント。TOCの理論と数字をベースにしながら、働く人たちのメッセージを読み解き、人と組織の潜在力を発動させて成長を支援するのが仕事だということです。
著者にとって処女作となる本書は、著者の専門であるTOCを解説するための本として計画されました。何度も頓挫しましたが、「小さく分ける」というキーワードを発見してから原稿が進んだそうです。
次に、本書の出版意図を知るために、「はじめに」を読んでみます。
「仕事でも家庭でも、理想とするイメージはなんとなくあるのに、なかなかそこに到達できない。そんな行き詰まり感やモヤモヤ感を抱えている方は少なくないでしょう」と著者は語りかけます。そして、その解決策が本書のテーマであり、タイトルでもある「小さく分ける」なのだと著者は言います。
ただ、ここには「小さく分ける」の具体的な方法やメリットについては書かれていません。そこで序章に読み進みますが、ここで「クイズ」が出題されます。
クイズ:あなたなら、どちらをやりますか?
あなたは八百屋さんの店長さんです。今日の仕事は、キャベツを12個切って、包んで、箱に入れること。
Aの方法:まず12個全部のキャベツを半分に切る→全部をラップで包む→全部を箱に入れる
Bの方法:1個ずつ切って→ラップで包んで→箱に入れる→これを12回繰り返す
広島のあるスーパーがこれを実験したところ、Aは8分20秒、Bは6分27秒だったそうです。多くの人がAの方が効率が良さそうだと感じて、だいたい9割の人がAを選ぶそうです。しかし実際はBが速い。これが「小さく分ける」の効果だと著者は言います。
続く第1章では、大多数の人が「効率が良さそう」だと感じる「大きくまとめる」の罠について論じられます。
その例として、スーパーなどでよく用いられる「まとめ買いがお得」が出てきます。実際にまとめ買いをしてみると、意外にたくさんの困ったことが生じます。モノが残って置き場所に困ったり、食べきれずに一部が腐ってしまったり。
そういう経験をしたことがあるのに、人はつい「まとめ買い」をしてしまいます。その理由は、「まとめた方が効率がいい」と思い込んでいるからだというのが、著者の主張です。
さらに人々が「大きくまとめる」方向を選ぶのは、そこに「評価される安心感」や「仕事やってる感」「貢献感」が加わるといいます。
そして第2章では「小さく分ける」の具体的な方法が語られます。その基本的な考え方に登場するのは「ボトルネック」です。
例として挙げられるのはトイレです。誰もがトイレに大量のトイレットペーパーを流すと詰まるということを知っていて、少しずつ流すようにしています。下水管がボトルネックであることをなんとなく理解しているからです。
この「少しずつ流す」が本書でいうところの「小さく分ける」です。限りなく小さく分けてしまうと効率は悪くなりますが、ボトルネックをスムーズに通過するくらいの大きさに分けることで、効率が最大化するというわけです。
次に出てくるのはある市役所での実例です。ボトルネックを意識して仕事を小さく分けたら、4倍のスピードで仕事が片づいたというものです。
その市役所では、市民に発送する通知をまとめてコピーし、それから全部を折って封入するという工程で作成していました。しかし通知の数は5000部。いつもコピー機の前に長い待ち行列ができていました。
そこで作業を50部ごとに分けたところ、コピー機の待ち行列がなくなりました。さらに、50部ごとに発送できるため、トータルでの市民に届くタイミングも早くすることができました。
この場合のボトルネックはコピー機で、「小さく分ける」は50部単位だったわけです。
このように、仕事のボトルネックはどこかを意識し、そこをスムーズに通過できる量まで仕事を「小さく分ける」ことで、その仕事が抱えていた問題を解決できる、というのが著者が本書で主張したい点です。
続く第3章では、なぜ「小さく分ける」と事業が儲かるかが解説されています。
最初の事例は、駐車場の不足に悩んでいた歯医者さんです。その歯医者さんには5台分の駐車場がありましたが、時間によってあふれてしまい、患者さんからクレームが出ていました。
駐車場の増設を考えているとき、ふと予約の方法を変えることを思いつきました。それまで30分単位で受けていた予約を15分単位にしたのです。
すると、1時間あたりの患者数は変わらないのに、駐車場のあふれが解消されました。おまけに患者さんがスムーズに流れるようになったため、カルテの準備などに余裕ができました。
このおかげで、その歯医者さんは数百万円かかる駐車場の増設をしなくて済んだということです。
続いて出てくる実例は、あの有名な日本酒「獺祭」です。獺祭は12階建ての温度管理されたビルの中でお酒を作っているため、一年中出荷が可能です。さらに、通常の酒蔵と違って小さなタンクで酒造りをするので、小ロット流通が可能です。そのためサプライチェーンが均等に流れ、ボトルネックがありません。
次の第4章は「小さく分ける」ことに対する抵抗感の解消法です。
およそ新しいことには抵抗がつきものです。著者は「小さく分ける」改革に起こりがちな抵抗を次の6つにまとめています。
(1)問題の存在を認めない、問題に同意しない
「それって本当に問題なの?」
(2)解決の方向性に疑問を感じる
「その方向で解決していいの?」
(3)具体的な解決方法に納得できない
「その方法で本当にいいの?」
(4)副作用を不安に思う
「でも、やったら別の問題が起きるんじゃない?」
(5)現実的な障害が気にかかる
「やりたいけど、○○があって無理」
(6)何か嫌、と未知への恐怖を感じる
「今までやったことないし……」
著者が提案する抵抗の解消法は、不安を見える化して共有することです。それにより、さらに良い改善策が見つかることもあると著者は言います。
そして次の第5章では、「小さく分ける」ための法則が5つまとめられています。
(1)ボトルネックを見つける
(2)作業単位を適切なサイズに分割する
(3)仕事を入れるタイミングを工夫する
(4)目標を具体的に分解する
(5)心理的な抵抗感に向き合う
そして、この法則を読者が自分たちの現場で使うための質問集が、読者特典としてQRコードからダウンロード可能になっています。セルフ出版だからこそのサービスです。
最後の第6章は、まとめであると同時に未来に向けた著者の想いが語られています。続く「おわりに」とともに読み通すことで、著者からのメッセージが受け取れます。
以上、駆け足でしたが本書の内容を概観しました。今ならキンドル・アンリミテッド登録者は無料で読めるので、ささっと試し読みしてみるのもいいでしょう。