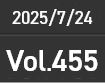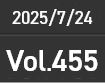聞いたことのない版元名ですが、これは著者が主宰するキンドル出版専門の版元名のようです。著者は「ことのはラボラトリー」を自分の屋号として使用しており、ドメイン名は「kot-lab.net」となっています。
まずは著者のプロフィールを紹介することから始めましょう。著者は1969年神奈川県生まれ。京都大学理学部を卒業後、阪神・淡路大震災のボランティア活動を経て毎日新聞社に入社、記者やデスクを務めました。
関心を持って取材したテーマは「原発」「医療」「科学」「研究不正」「災害・防災」などで、2019年に会社の早期退職募集に応じて退社。以降はフリーライターとして活躍しています。
2024年春からは、アマゾンの電子書籍出版をサポートする「キンドル出版プロデューサー」の仕事も始め、「本を出版したい」という人の願いを叶えるために、その見本的な作品として本書を世に出しました。キンドル出版であるため、キンドルの電子書籍のみの発行であり、紙の本はありません。
本書の「はじめに」の冒頭には、こんな文章が載っています。
「作文が大の苦手でした。夏休みの宿題の読書感想文がどうしても書けず、提出しなかったこともあるほどです」
「新聞記者」というと、「話すより書く方が得意」といった人を想像してしまうのですが、著者はそういう人ではありませんでした。それなのに23年間の新聞記者生活を全うできた理由は、「文章は才能ではなく技術である」という考えを信じて実践してきたからです。その方法論を説き明かしたのが本書というわけです。
著者は現在、フリーライターとして各方面で活躍していますが、それでも「自分に文章を書く才能を感じたことはありません」と言い切っています。著者自身の存在が、「文章は才能ではなく技術である」という論の証明なのだそうです。
本書はアマゾンのキンドル・ダイレクト・パブリッシング(KDP)というシステムを利用して出版されています。これは誰もが原稿さえ用意できれば本を出版できるという個人出版のハードルを下げたもので、アマゾンからしか販売できませんが、多くの場合百万円単位の費用を要する「自費出版」がほとんど無料で実現できます。
ただし、原稿ファイルの取扱いやアップロードの仕組み、値付けや印税率の設定など細かいことを全部自分でやらなければならないため、技術的なハードルは決して低くはありません。それを理解したので、著者はキンドル出版プロデューサーとして本を出したい人のお手伝いをしているわけです。
それでは、本書の目次を紹介しましょう。
・はじめに
・第1章 文章への苦手意識と新聞記者生活
・第2章 何を書くか。どのような構成で書くか
・第3章 タイトルと体裁~文章は見た目が9割
・第4章 文章術
・第5章 「文章が苦手」から脱するために
・おわりに
・著者プロフィル
第1章の紹介は飛ばします。著者が文章を書くことを苦手にしていたという話はもう触れましたし、著者の新聞記者生活は興味のある人が本書で読めばいいと思うからです。それよりも本書のキモである「文章は技術である」という部分が重要でしょう。
第2章はその基礎編です。第3章が応用編、第4章が上級編という感じで読み進めればよいのだと思います。
第2章の構成は次のようになっています。
・ネタ探し
・自分が面白いと思えばネタになる
・自伝は関心を持たれる
・素材集め(取材)
・見出しを考えてみる
・構成を決める大切さ
・構成のパターン
・「つかみ」が大事
最初の「ネタ探し」は、簡単に言えば「常にアンテナを張っておき、自分の好奇心を刺激することを素早くキャッチすること」です。ただし、新聞記者のネタ探しと、SNSなどに投稿する記事のネタ探しは重さがまるで違います。
「ネタ探し」について、著者は読者にこうアドバイスしています。
「新聞記事に限らず、ネタになるかどうか迷ったら、『自分が面白いと思うか』『自分の感情が揺り動かされたか』を判断基準にしてみてください。そう考えると、身の回りにネタはたくさん転がっていると思いませんか?」
読者への参考として、著者が若い頃、茨城県水戸支局で担当していた連載記事のタイトルが挙げられています。
・茨城弁を聞き取るために知っておくべきことは何か/「イ」と「エ」に区別なし
・なぜ県内には「根本」姓が多いのか/祖は将門の乱で活躍の藤原秀郷
・ガマの油は本当に効き目があるの?/主成分除かれ、今はスキンケア用
・なぜ茨城で汚職がはびこるのか/公共事業依存と政治的無関心
「自伝は関心を持たれる」というのは、その人の自伝がその人だけのオリジナルネタだからです。新聞などの「人生相談」が人気なのは、他人の人生が読む人の心を動かすことが多いからです。なので、「自分の人生なんて平凡で面白くない」と思っている人は、見方を変えて深掘りする必要があるでしょう。
「素材集め(取材)」の項で、著者は「文章は素材集めが9割、とも言えます」と書いています。素材がない、つまらない文章はどんなに書き手の技量が高くても、読んでもらうことはできません。
何を書くかを決め、素材も集めたら、文章を書き始める前に見出し(タイトル)を考えるべきだと著者は言っています。メールなら「件名」にあたるものです。著者も新聞記者時代、自分で仮の見出しを考えてから記事を書き始めていたそうです。
見出しを考えずに文章を書き始めてしまうと、何が言いたいのか理解できない原稿になりがちだといいます。何がポイントなのかが明確になっていないからです。これは新聞記事に限らず、SNSの投稿やメール、書籍の原稿など、文章を書くあらゆるケースに言えることだと著者は力説しています。
文章を書き始める前の仮の見出しは、文章がブレないためのガイドのようなものなので、文章が完成したら変更してもいいそうです。
「構成を決める大切さ」というのは、特に長い文章を書く時のヒントです。参考として、朝日新聞の記事が掲載されています。
***
米民主党のバイデン大統領(81)は21日、11月の大統領選から撤退する意向を明らかにした。現在の大統領任期は全うする。大統領選に向けた民主党の公認候補としては、カマラ・ハリス副大統領(59)への全面的な支持を表明した。投票日まで4カ月を切る時期の立候補断念は極めて異例で、民主党は後任選びを急ぐ。
***
これは記事の「前文」にあたる文章ですが、ここに記事のポイントや読者の疑問である「後任候補は?」に対する答えが記され、最後の一文でニュースが持つ意味や意向表明が及ぼす影響を示しています。この文章があれば、後はその内容を順に詳しく書いていくだけです。
著者は現役の新聞記者時代、この前文さえ決まれば構成はそれほど意識して考えなかったといいます。前文は読者にとっては記事の要約やポイントを知るためのものですが、書き手にとっては文章のゴールにたどり着くための地図の役割を果たしています。
多くの人が書いている文章は新聞記事ではないので、前文のような文章を最初に持ってくる必要はありません。その代わりに著者が勧めているのが、「目次(構成案)を最初に作る」ということです。
その作業を、著者は本書の制作を例にして説明しています。
まず「元新聞記者のライティング術」というタイトルが決まったら、次にテーマに合わせて盛り込める項目をスマホにどんどん書いていきました。それを自宅に戻ってからパソコンのワードにコピペし、章別に振り分けていきました。
こうしてできた目次は、最後まで書ききるための地図の役割を果たしました。ゴールまでの詳細が目次に示されているため、書き手は寄り道したり迷走したるすることなく完走することができます。すなわち、目次は読者のためだけではなく、著者のためにもあるということです。
そのような文章の構成ですが、いろいろなパターンがあります。最も有名なのは「起承転結」で、これは漢詩の構成法から来ています。ほかには「序破急」「序論、本論、結論」「PREP法」「SDS法」「逆ピラミッド型」などが知られています。
章末の「『つかみ』が大事」という項には、忙しい現代人に文章を読んでもらうためのコツが書かれています。書籍ならば、本のタイトルとサブタイトル、キャッチコピーで読者の関心を惹き、「まえがき」や「はじめに」で「この本を読みたい」と思わせ、目次で「これは買わねば」と財布を取り出させなければ売れません。
最近は「タイパ(タイムパフォーマンス)」なる言葉が流行語となり、イントロの長い曲がスキップされてしまう、映画を早送りで肝心なところだけを視聴するといった時間コスト重視のライフスタイルを優先する風潮となっています。そのため、あらゆるコンテンツにおいて「つかみ」の重要性が増しています。
そこで再び注目されているのが新聞の「前文」というわけです。雑誌ではタイトル下の「リード文」と呼ばれるものが前文に相当します。学会の論文などでもそれに相当する「サマリー」という部分があります。
新聞の前文のように、読み手の必要な情報がすべて冒頭に置かれ、それ以降で詳細を説明する方法は、まさに「つかみ」です。文章を書く時にそれを意識すると、より読者に伝わり、読んでもらえる文章になるかもしれません。
続く第3章の内容は、次のようになっています。
・文章は内容だけではない
・読んでもらえるかどうかは表紙次第
・タイトルと件名
・字下げ問題
・一つの段落が長いと読む気がうせる
・余白は大切
・漢字とひらがな
・新聞の表記ルール
・自分の好みで統一を
最初の「文章は内容だけではない」という項目は「?」と感じた人もいることでしょう。「文章から内容を取ったら、何が残るの?」と。
著者が言いたいのは、「文章も見た目が大事」ということです。それを次の「読んでもらえるかどうかは表紙次第」という項目で説明しています。
***
著者が有名人や知り合いでもない限り、その本を手に取ってくれるかどうかは表紙次第です。どんなに素晴らしい内容の本でも、手に取ってもらわないことには内容を伝えることはできません。素晴らしいかどうか、評価してもらうことすらできないのです。そう考えると、「見た目が9割」どころか、「見た目が10割」だとは思いませんか?
***
著者は「文章にも見た目という非言語の要素があり、文章の中身を読んでもらうためにも見た目には気をつけなければならない」と言っています。先の例は本の表紙でしたが、著者の言う文章の見た目には、ほかにもたくさんの要素があります。
それは、文章のレイアウト、段落の分け方、フォントの種類や大きさなどです。たとえば最近の実用書やビジネス書によく見られる、本文中に太字や傍線、マーカーなどを入れて重要なところを強調するやり方も、見た目の一種です。
印刷物でなくても、電子メールでも見た目は重要です。長い文章をだらだらと書くよりも、適当な長さで改行したり、段落間に空行を入れたりして読みやすさを工夫すると、受け取った相手も良い印象を持つでしょう。
SNSやショートメッセージでは、画像や絵文字、ハッシュタグなどの非言語要素が重要になります。視覚的な要素も印象を大きく左右するからです。
さらに「見た目」の要素が大きくなるのが「手書きの文章」です。手書きの文字には書き手の人柄が表れますし、デジタル全盛で活字が当たり前の現代では、「自分のために時間と手間をかけてわざわざ書いてくれた」という思いが伝わることが付加価値になります。手紙の場合は封筒や便箋のセンスも大事です。
文章の「見た目」として、著者は「漢字とひらがな」という問題も提起しています。どの言葉を漢字にして、どの言葉をひらがな、あるいはカタカナで表記するかは書き手のセンスが問われますが、重要なのは「統一する」ということです。文字統一ができていないと、真剣に書いていないという印象を持たれます。
次の第4章では、「文章に正解はない」という項目から始まります。著者は昔の自分を省みて、「文章が苦手だったのは、正解がわからなかったからかもしれない」ということに思い至りました。
いかにも理系の人らしい考え方ですが、文章には「これが正しい」という唯一無二の答えがありません。存在するのは、より良い文章を書くためのコツや方法論です。以下、そのコツが列記されていきます。
ひとつは、「1文は短い方がいい」ということ。ふたつめは「文章は書かれた順に読まれる」ということ。以下、「読者に受け入れ準備をしてもらう」「専門用語やカタカナ語は避ける」「読み手の立場に立つ想像力」「具体的に書く」「順接の『が』は控えよう」「です・ます調か、だ・である調か」「カギ括弧の有効利用」「英訳しやすいか意識してみる」と続きます。
次の第5章では、わかりやすい文章を書き、苦手意識から脱するための具体的な方法が示されます。項目を列記します。
・信頼できる人に読んでもらう
・1人の場合は?
・タイトルで「ゴール」を定める
・とにかく書き、後で整える
・事実関係は正確に
・「文章が苦手」の原因
・苦手克服のために
本書を読めば必ず文章を書くのが苦手でなくなるかどうかは、著者と読み手とのマッチングによりますが、少なくともヒントにはなるでしょう。
キンドルアンリミテッドに加入している人は無料で読めるので、試しにさらっと読んでみるといいと思います。