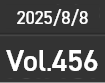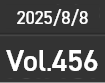今のところキンドル・アンリミテッドに入っているので、登録している人は無料で読めます。
著者は著名な社会学者、心理学者、評論家で、早稲田大学名誉教授。ニッポン放送の「テレフォン人生相談」のパーソナリティを1972年から務めていることでも知られています。
600冊を超える著書があり、『自分に気づく心理学』『「大人になりきれない人」の心理』(PHP文庫)、『人はどこで人生を間違えるのか』(幻冬舎新書)などのベストセラーがあります。
本書のエッセンスは「はじめに――人は「弱点を隠そうとしない人」を好きになる」に書かれていますので、要所を引用しながら対応する本文を紹介するかたちで進めていきたいと思います。
***
ノーと言っても好かれる人がいる。しかしイエスと言っても好かれない人がいる。なぜか? それがこの本のテーマである。「こんなに真面目に生きてきたのに、こんなに勤勉に努力してきたのに、こんなに頑張って生きてきたのに、何も悪いことはしなかったのに、善人のつもりなのに」。だけど人生がどこかおかしい。
***
この冒頭の文章に対応する本文は、1章の「なぜ自分らしく生きられないのか」です。1章の見出しを並べてみます。
○「無理している自分」に気づいていますか?
・なぜ相手にとって“都合のいい自分”を演じてしまう?
・「悩み」を隠すための“明るいふり”はあなたをダメにする
○「こうであるべき自分」は今すぐ捨てたほうがいい
・「自分を出したら嫌われる」という思い込み
・「ありのままの自分」のほうが好かれる
○どうすれば人前で“自分”を出すことができるか
・結果を気にしすぎるから「現在」を楽しめない
・「理想」はあなたが無駄だと思っていることのなかにある
・悲観論者はいつまでたっても“素敵な自分”に気づけない
著者の言う「無理している自分」とは、人から気に入られるために自分の感情を偽ることを指しています。人に好かれようとするあまりに相手の気持ちを推測して、自分の気持ちを裏切り、そのことで気分が晴れずにいます。自分の気持ちに正直にしていれば気持ちが晴れるのに、気が弱い人はそれができずにいます。
また、「こうであるべき自分」とは、自分の本当の気持ちを隠し、何となく相手に好かれるのではないかと勝手に推測した自分像を意味しています。しかし、その虚像が相手から好かれることはありません。
著者は本書でたびたび「自分を出す」という表現を使いますが、それは何か奇抜なことや衝動的なことを意味しているのではありません。ただリラックスして防衛的な気分にならず、好きなものを好きと言い、嫌いなものを嫌いと言うだけのことです。著者は自分を偽って本音を隠して生きるよりも、そうやって自分を出して生きるほうが相手から好かれると言っているのです。
ところが、世の中には「自分を出したら嫌われる」と思い込んでいる人がたくさんいる、と著者は言います。その人はもしかすると自分を出すことを「わがままにふるまうこと」と勘違いしているのかもしれません。
***
リラックスして椅子に腰掛けながら相手と話をしているときには、相手と心がふれあっている。(中略)自分を出しているときには相手と心がふれあっている。相手が自分のことをどう思っているかを気にしていないときには相手と心がふれあっている。それが大切なのである。それが「こころ」なのである。
***
「自分を隠しているときには不安で緊張している」と著者は言います。そして、そのストレスが人を拒否している雰囲気を作ってしまいます。その結果、たとえどんなに立派に行動しても、その人は人から好かれません。
そもそも、「立派に行動したら好かれる」という考え方が間違っているのだと著者は言います。「せいぜい自分にふさわしい程度の立派さでいいのである」ということです。
こうして「自分を出す」ということが感覚的にわかってくると、その先に進むことができます。
ふたたび「はじめに」に戻ります。「自分は世の中から正当に評価されていない」と不満を持つ人の原因を、著者はこのように分析しています。
***
その原因は何か? おそらくどこかで人生の重荷を背負うことを逃げたに違いない。本人が意識していないとしても、心はそれを知っている。人間の大きさとか深さとかいうものはどこで決まり、どこで出てくるのであろうか? それは人生の重荷をどこまで広く背負ったかということで決まるのではなかろうか。
***
著者の言う「人生の重荷」とは、しなければならない嫌なこと、越えなければならないつらいこと、言い換えると「人生の修羅場」のことです。そこから逃げてばかりいる人は、決して人から好かれず、幸せになることもありません。
たとえ自分の意識では忘れていても、心の奥底では自分が「逃げた」ということをはっきりと記憶しています。背負うべき重荷を背負わずに、言い訳ばかりしているから、その人は安心して「自分を出す」ことができません。だからいつまでもリラックスすることができず、人から好かれません。
***
どんなに成功しても、自分を尊敬できない人はどういう人であろうか。社会的に成功しても、目がキョロキョロしていて落ち着かないという人はどういう人であろうか。それは修羅場から逃げてきた人である。どんな小さな仕事でもどんな大きな仕事でも、公的なことでも私的なことでも、その過程で修羅場というのがある。正念場といってもいい。もっともつらい場面である。(中略)この修羅場から逃げたら、どんなに成功しても心の落ち着きは得られない。
***
また「はじめに」に戻ります。
***
広く人生の重荷を背負えば、その人は鍛錬されて心が大きくなる。そして何よりも誇りが生まれる。名誉とか、権力とか、財産とかが絶対に与えることのできない誇りが、静かにその人の心のなかに生まれてくる。それが人に安定感を与える。落ち着いた雰囲気というのはそこから生まれてくるのだろう。人生の重荷から逃げて、あとで坐禅をして修養しても心の平静は獲得できない。
***
続いて著者は「人生の重荷を背負った人は、無駄なエネルギーを使わない」と言っています。自分の弱点ややましさを隠すことにエネルギーを使わなくなるため、疲れにくくなり、勤勉な努力が成果につながります。だからこそ、人生の重荷=修羅場から逃げてはいけないということです。
「はじめに」の次の部分で、著者は「失うことを怖れてはいけない」と言っています。失うことを怖れていると、それだけで疲れてしまいます。失うまいと思うことがストレスの原因になります。
***
失いそうになるときに人は悲鳴を上げる。苦しくてのたうちまわる。しかし、しがみついてはいけない。努力することはいい。しかし、しがみついてはいけない。執着は人を滅ぼす。一時の心の安心のためにそれ以降の人生を破壊する。
***
著者はこう言います。「失うものはもともと自分のものではないのだ」。しかし、失いたくない人はそう考えません。今自分が手にしているものは、未来永劫自分のものであり、それを失うことは自分の身を切られるのに等しいと思っています。
手にしたものを永久に持ち続けることなど誰にもできません。仮にそれが永久不滅だとしても、自分は不老不死ではないのですから、どこかで失う局面が訪れます。だから、失いたくない人は変化を認めたくない人ということになります。
変化を認めたくない人は、自分を中心にものごとが回っていると考えているのと同じです。天動説の人は相手の気持ちに寄り添うことができませんから、やはり人から好かれません。
著者は「もともと人は裸で生まれてきたのである。人は自分を出したときに強くなる」と言っています。自分を出せる人は、地動説の人です。
「努力しながらも、なぜかうまくいかない人は、あまりにも安易に人に好かれようとしたのである」というのが、本書における著者の基本的な考えです。安易な方法とは、従順にふるまうとか、ご馳走をするとか、お世辞を言うとか、相手を喜ばす話をするとか、何かを与えるとかなどのことです。
つまり、本質的なことではなく、相手に迎合した小手先の小細工に頼る対処法を選んだということです。著者はそんなことよりも勇気を出して自分をさらけ出すことを勧めています。
小手先のテクニックで相手を喜ばせようとするのは、自分を出さないだけでなく、相手の本質も見ていないことを意味します。自分の頭の中で考えた相手の虚像に迎合しているのですから、そこに本物のコミュニケーションは生まれません。
***
自分をさらけ出すという勇気は修羅場を呼ぶかもしれない。しかしそれが本当に好かれる方法であるときもある。人生の重荷から逃げて人に好かれようとどんなに努力しても、好かれることはない。その努力は無駄になるばかりではなく、ずるい人に利用されるだけのことである。そんな努力はしないほうがいい。
***
今度は「あとがき」に飛んでみます。ここでは冒頭にこんな文章があります。
***
生きることがつらい人は「人の強さ」「理想的な生き方」という意味を勘違いしている。自分の弱点を出せるということが「内面的強さ」を表していることなのである。弱点のないことが強い人ではなくて、弱点が出てもその場で心理的に混乱しないということが強い人なのである。
***
ここを理解していない人が、いくら自分の思う「理想の人」を演じようとしても、心は安らがず、つらい思いが重なっていきます。
***
生きることがつらい人の願う「理想の人」を彼らが演じても、普通の人はその人を理想の人とは思わない。弱点を隠して理想の人を演じても人は親しみを感じない。
***
つまり、著者は「理想的な生き方を勘違いしている人」には、その人らしい固有のものが感じられず、だからまわりの人が親しみを持てないのだと言っているわけです。
***
生きることがつらい人の願う「理想の人」には心がないから、その人の周りに集まる人も皆心のない人である。心の酸欠状態である。酸欠状態だから何かわからないけど「苦しい、苦しい」状態が続く。
***
このような状態に陥ってしまうのは、その人が「弱点=悪」と思い込んでいるからです。その気持ちがあるから他人の弱点をやさしさを持って見られません。そして自分自身の弱点に対してもやさしさのない目で見ています。
***
自分を冷たい目で見ることが自分の人生をつらくしている。さらにそのうえに相手に対する冷たい目がある。それがつらい人生という形で自分に返ってくる。
***
「あとがき」の後半は、熟年離婚をしたある夫婦の話に移ります。
奥さんはご主人が自分に対する関心を失っていると思っていました。
ご主人は嫉妬深い男と思われたくなくて、奥さんに根掘り葉掘り聞くことを控えていました。
しかし、ご主人の隠した嫉妬心は日常生活の別の面に出ました。奥さんに掃除のことからお金の使い方までネチネチと問いただしたのです。奥さんはすっかり嫌気がさしてしまいました。
著者はこうまとめています。
***
もしストレートに自分の感情を出していればご主人はいやがられないでいたのである。いやがられるどころか奥さんは毎日がわくわくして「素敵な女」を演じていたに違いない。
***
もうひとつエピソードが続きます。
***
ある「明るい人」が自殺した。周囲の人は「あの明るい人が!」と驚いた。そして「信じられない」と言う。その自殺した人は、好かれるために明るい性格を無理に演じていた。しかし実は心の底では孤独で自分の無力を感じていた。
***
著者が言うには、「本当は自分に自信がない。その人は自信のなさを隠すために社交的に明るくふるまっていただけ」とのことです。そして「そういう人は無理に明るい性格を演じても、なんでも話せる親しい友達がいない」という傾向が見られるそうです。
***
もしこの人が「実は淋しくて自信がないんだ、だからついつい大きなことを言ったり、わざと明るくふるまったりしてしまうんだ」と自分に正直になれていたら、親しい人ができたであろう。
***
自分を出して、本当の自分の感情を表現できていれば、この人は楽しく生きられたかもしれない。最後に、著者はそう結んでいます。
店長日記で、メルマガで、SNSで、潜在顧客に何かを訴えかけるときに、思い出してほしい1冊です。