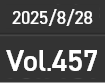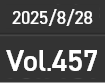日本実業出版社という版元は、実業之日本社という老舗出版社と間違えられることが多い創業75年の中堅出版社で、おもにビジネス書や実用書を出版しています。大阪に本社があり、東京には東京本部を置いています。
創業の地は広島で、後に大阪に本社を移しました。「働く人の仕事に役立つ本」を出版するという方針で、『教養としての「金融&ファイナンス」大全』、『決算書の比較図鑑』、『子どもが本当に思っていること』、『「副業講師」で月10万円無理なく稼ぐ方法』、『英語が日本語みたいに出てくる頭のつくり方』などのベストセラーがあります。
本書の著者である池田千恵氏は「朝活」で著名なコンサルタントで、株式会社朝6時の代表取締役で作家でもあります。福島県生まれで慶應義塾大学総合政策学部卒業後、ワタミ株式会社、ボストン コンサルティング グループを経て独立し、2009年に刊行した『「朝4時起き」で、すべてがうまく回りだす!』(マガジンハウス)がベストセラーとなり、「朝活の第一人者」と呼ばれるようになりました。
会社員時代には趣味の飲食にまつわる資格を7つ取得し、会社の許可を得た「週末起業」でパンやワイン、チーズの知識を教える先生としても活動したそうです。近著には『週末朝活』(三笠書房)、『ME TIME 自分を後回しにしない「私時間」のつくり方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがあります。
本書は少し長めのプロローグに始まり、目次を挟んで第1章から第5章まであり、読了するとひとつのカリキュラムが修了する感じでまとめられています。
今回は最初に紙幅を多めに費やしてプロローグを紹介し、次に第1章~第5章という順番で紹介していきたいと思います。プロローグは通常の本よりもかなり長めで、著者の言いたいことが凝縮されていますから、まずそこをよく理解し、それから各論に入っていくのが本書の読み方として良さそうに思えたからです。
プロローグでいきなり目に入るのが、本文の太ゴシックで強調された部分に引かれた真っ赤な傍線です。最近はこういうデザインの本が増えました。昔は傍線などは読者が自分で判断して書き込むものでしたが、これもユーザーサービスの一環なのでしょう。私も本を作るお手伝いをしているとき、よく編集者から「太ゴシックと傍線もお願いします」などと言われたりしています。
プロローグのタイトルは、「アウトプットの質があなたの人生の質になる」です。そしてページをめくると最初の大見出しが「『素』のままで仲間が増える『アウトプット』を始めよう」となっています。
これらの意味は、少し先の本文にある「この本で紹介しているアウトプット法を学べば、理解され共感され、協力者が増え、仲間とともに楽しく人生を過ごせるようになります」で理解できるでしょう。
さらに読み進むと、本書での「アウトプット」の定義が書いてあります。すなわち、「あなたの考えや活動を誰かに知ってもらい、協力を得られるようにするための働きかけ全般」が本書でいうアウトプットであるというのです。
ここまで読んで、「ん? 自分が思っていたアウトプットの定義と違うな」と思う人も多いでしょう。通常、アウトプットには特定の目的はなく、ただ自分が出すものすべてのことを指すというのが、一般的なアウトプットの定義ではないでしょうか。
著者はそうではなく、自分のアウトプットに目的を定め、それに触れた人たちに自分に対する共感を持ってもらおうと言っています。
***
つまり、この本で学べるのは、自分自身の「中身」をどうアウトプットするかの方法論です。具体的には、自分自身の考えや経験を、「あうん」の呼吸で知ってもらっている仲間から広げて、一歩越えた先にまで伝える方法を「書く」「話す」「作る」「動く」に分けて具体的に解説します。
***
この「書く」「話す」「作る」「動く」がそれぞれ第2章から第5章に分かれて展開され、最初の第1章では心構えを勉強するというのが本書の構成です。
プロローグの小見出しに、興味深いものがありました。
「うまくまとめることはAIに任せ、自分の「中身」を外に出す」
突然、AIという言葉が出てきて驚きますが、著者はアウトプットの方法論にAIを活用すべきだと力説しています。うまくまとめ、わかりやすい表現に直し、伝わる工夫をすることはAIの得意技なので、それを使わない手はないということです。
これまで、その部分に引っかかって上手なアウトプットができずにいた人にとって、AIを活用することで積極的な「自分を出すこと」、すなわちアウトプットが可能になると著者は言っています。
そして、次の一文が大事です。
「本書では、すでに世の中にあるものをアウトプットする方法ではなく、あなた自身の考えや、過去の経験、未来への希望をアウトプットする方法を紹介します」
AI時代には「どこかにあるもの」「誰かと同じ意見」はあまり意味を持ちません。それらはプロンプトを入れればAIが1秒で返してくる答えに入っています。だから、自分自身にしかないもの、オリジナルの経験こそが価値を持つわけです。そのために、自分自身の中身をアウトプットすることが大事だというわけです。
そして著者はこう言います。「自分にとって『大したことない』と思っている経験ほど、周囲にとって価値があるものです」と。「自分にしかないオリジナルの経験」と言われてしまうと、「そんなの自分にはない」とマイナーな気持ちになってしまいそうですが、「いや、あなたには必ず価値のある内容がある」と著者は励ましてくれています。
自分に自信が持てないという人に対しては、著者はこう言っています。「不安や弱さこそ最高のアウトプットです」と。弱さを認識しているということは、「私はここが苦手で、できない」と自己理解ができている証拠だからです。
ひとたび自分の苦手をアウトプットしてしまえば、「私もそうだよ」という共感者も現れるでしょうし、「自分はそれが得意だから手伝ってあげるよ」という協力者も登場するでしょう。その人たちはアウトプットしなければ見つからなかった仲間です。
そのことを推し進めていくと、「自分商品化」につながります。自分の強みや弱みを隠さずアウトプットしていくうちに、自分が客観視でき、自分の価値が見えてきます。すると、やがては自分のできることに値付けができるようになるでしょう。
たとえば、今の仕事がつらいと感じている人は、そのことを嘆くのではなくアウトプットのネタにしてやろうと思うことで、前向きになれます。実際に著者の周りにいる多くの人たちは、アウトプットで人生を変えることに成功しています。
著者はまた、「アウトプットは、あなたから滲み出る『だし』である」と言っています。その「だし」は単独のかつおだしとか昆布だしではなく、さまざまなエッセンスがブレンドされたオリジナルの複合だしです。
たとえば、著者は15年間「朝活」をテーマに活動してきました。その途中から、会社員がアウトプットを練習するコミュニティ「朝キャリ」もスタートさせ、のべ400人のアウトプットに関する悩みを解説してきました。
それらの合わせだしによって味付けられたのが本書であるわけです。
これから意識してアウトプットを始めたいという人には、「まず週末を活用しよう」と著者は勧めています。平日は何かと忙しいので、平日はインプットだけにとどめ、週末に15分からできるアウトプットに意識して取り組むのがいいそうです。
ここでようやくプロローグを終えて、第1章に入ります。第1章は「マインドセット編」と名づけられ、「インプット偏重からアウトプット志向に変わる」とサブタイトルがついています。インプットしすぎの消化不良から抜け出し、「アウトプットしてからインプットする」という流れを習慣化しようという章です。
一般に、学びすぎは視野を狭くし、「私なんてまだまだ病」にかかります。しかも、借り物の言葉を使いがちになるので、思考が薄くなります。そこでアウトプットの出番です。最初のうちは、他人ではなく「過去の自分」に語りかけるようにしてアウトプットしてみましょう。今の自分よりも足りない過去の自分になら、恥ずかしくなく語りかけることができるはずです。
第2章からは各論です。まずは「書く」ことから。サブタイトルは「SNS・日記、『書き出す』でアウトプットの質を高める」です。
「書く」アウトプットのコツは、「いいこと」を書こうとせずに「好き」を書くことです。たとえばSNSで「好きなこと」を書いたり、日記に自分のチャレンジのプロセスを記録するなどです。
「自分のこんなところが嫌!」を書き出してみるという技もあります。「ついつい出る職業病」などは共感者が集まるでしょう。「こうしたらいいのに、もったいない」というテーマなら、コメントがたくさんつくかもしれません。
そうして書くことに慣れていったら、受講したセミナーや読んだ本の感想をSNSにアップするというアウトプットの王道に進みます。そうしてアウトプットに慣れていけば、いつの間にかあなたのアウトプットは自己満足から他者に役立つものに進化していくはずです。
次の第3章は「話す」編です。サブタイトルは「何を誰に伝えるかを明確にする」。
著者は昔、人前に出るのが苦手で、書くことよりも話すことが苦手だったそうです。いまだに話すことのほうが書くことよりもハードルが高いと感じていると書いています。
そんな著者は話すことについて3つの小さなテーマを持ちました。
(1)どんな小さなアウトプットにもゴールを決める
(2)失敗はつきもの、教訓を次に活かす
(3)過去の失敗を思い出して「うわあ!」となったら、「でも大丈夫」と唱える
(1)は狙いを定めるという意味です。たとえば複数の人の前で話すときでも、「あの人がうなずいたら成功!」と決めておけばいいのです。すると漠然とした不安は消えていきます。
(2)は、とにかく数をこなそうということです。小さなつまずきにとらわれるのではなく、「はい、次!」と意識を前に向けることで、気持ちが失敗に執着してしまうのを防げます。
(3)は、呪文やおまじないのようなものですが、それを習慣化することで気分をリセットすることができます。過去にやらかしてしまった恥ずかしいことから遠ざかるには、こういうルーチンが効果があります。
話をまとめるのが苦手な人、すぐに話題が横道にそれて脱線してしまう人は、「とにかく話すことを3つにまとめる」というクセをつけるといいと著者は勧めています。
たとえば「今日のランチはカツ丼にしたいと思いました。理由は3つです」と最初に言ってしまい、こじつけでも何でもいいのでとにかく3つの理由を話してしまう。そういう練習が効果的だそうです。
第4章の「作る」編は、「アウトプットの核を整えマネタイズを目指す」というサブタイトルがついています。「作る」とは、自分のアウトプットを作品に整え、マネタイズを目指すことです。
この場合、ネタ切れが心配になりますが、アウトプットが習慣化していけばいくほど、ネタ切れには困らなくなるという著者の経験談がついています。いよいよ困ったら、ニュースをネタにすればいいそうです。
ただし、何かの要約はNG。単なる要約なら、今やAIのほうが得意ですから、人間が勝負してもかないません。必ず自分の視点を入れたアウトプットにしましょう。
最後の第5章は「動く」編です。「いよいよアウトプットを実践する」というサブタイトルがついています。著者の言う「動く」とは、アウトプットしながら行動できるようになることです。
アウトプットしながら動くことができるようになると、「オン」と「オフ」の境界がなくなります。公私混同が自分の中で当たり前になります。著者は、「これからは公私混同の時代です」と言っています。
会社モードの自分、プライベートモードの自分を切り替えて本心をスイッチするのではなく、自分自身の人生目標に向かって素のままで行動できるようになるため、気持ちが楽になります。
本音で仕事に向き合うことで、「なりたい自分」を明確化し、そこに向かってストレートに向かっていけば、「私は○○になりたい!」と公言できるようになるでしょう。それが実現の早道です。そしてそれが、仕事での利益にもつながるはずです。
今の時代、アウトプットが必要ない人はほとんどいないでしょう。特にお客さまとじかに接する立場の仕事についている人は、毎日がアウトプットの連続のはずです。本書はそんな人たちの何かに役立つエッセンスが詰まっています。