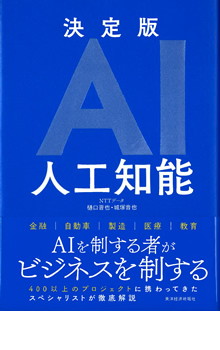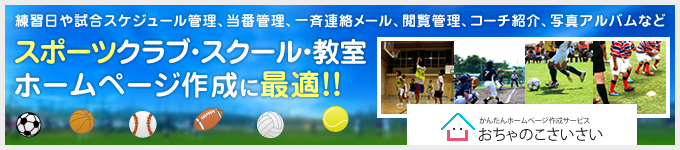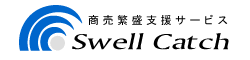「たかがAI、されどAI号」 |
 |
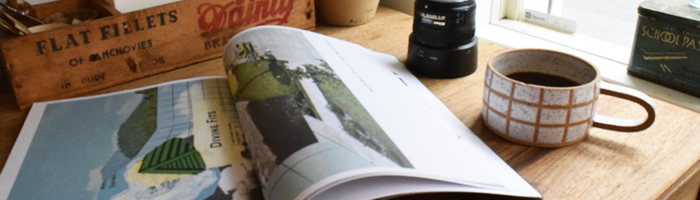
「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。
2018年の日本で「AI(人工知能)」という言葉を知らない大人はほとんどいないと思いますが、この言葉がいつから存在するかはあまり意識されていないのではないでしょうか。
つい最近の流行語と思っている人には意外かもしれませんが、AI=Artificial Intelligenceという言葉が誕生したのは1955年(昭和30年)で、翌年のダートマス会議(ダートマス大学で1956年の7月から8月にかけて行われた世界初の人工知能会議)で発表されました。
考案者はプログラミング言語LISPや、今のクラウド技術の根幹であるタイムシェアリングの概念を発明したジョン・マッカーシーです。それ以前に存在した電子頭脳(Electrical Brain)という言葉がAIに置き換えられたのは、電子頭脳という言葉には知性という意味が含まれていないからです。
AIはコンピュータ技術の発展とともに3つの段階を経て進化してきました。第1世代はプログラム可能な計算機。つまり「コンピューター」です。次の第2世代は知識ベース処理を行うコンピューターで、予測変換や大規模検索が相当します。迷惑メールフィルターや学習機能付きかな漢字変換などもこの技術を使ったものです。
今のAIブームは第3世代の技術が背景となったものです。コンピューターが「特徴量の抽出を学習すること」により擬似的な知性を生み出すもので、「ディープラーニング(深層学習)」の手法がその背景にあります。人間に勝利した「アルファ碁」やソフトバンクの「ペッパー」も、このレベルのAIです。
ただし一般大衆の間では、AIという概念が正しく理解されず、バズワードとして抽象化されている懸念があります。欧米では「スマートスピーカー」と呼ばれている商品が日本では「AIスピーカー」と呼ばれていることなどもその例の一つです。
言葉に踊らされ、過度の期待を持たされて失望するのは幸せなことではありません。AIを便利な道具として使いこなすためには、その可能性と限界をきちんと理解しておくことが必要です。今回の「オススメ参考書」では、そのために役立つ本を紹介します。
おちゃのこ最新ニュース
|
今週のトピックス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!
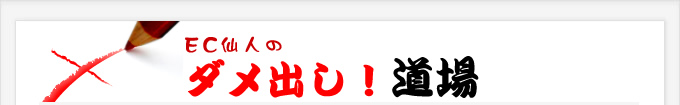
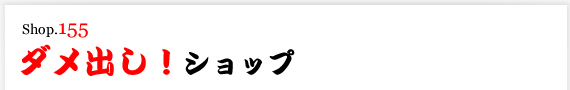
 ご懸念の「レスポンシブデザイン」に関してはPC、スマホともデザインクオリティでは問題ないと思います。 それよりも、コンテンツや商品の構成、魅力や強みのアピールなど、中身のほうに多くの課題があると感じました。 コーヒー、お茶、お酒などは嗜好品であり、また近所のスーパーや量販店で簡単に手に入る商品でもありますが、ネット上でもとても多くのお店がひしめき合っている超競争業種の一つです。 それだけに、近所に買いに行けばその日のうちに手に入る物を、わざわざ遠方のネットショップからお取り寄せするには、それなりの動機付け、「特徴」、「魅力」や「強み」が必要です。 よくよくお話を聞いて、商品ページを一つ一つ見ていけば、ようやくヴォアラさんの「強み」はいろいろな国、産地の「小規模農園」に特化して、コーヒーの国際品評会の審査員もしている社長自らが、その年、そのシーズン毎に異なったコーヒー豆を買い付け、自社で焙煎し販売している、鹿児島県内に(カフェはない)豆だけの実店舗を4店舗展開されている正に「コーヒー豆の専門店」であることだとわかりましたが… しかしながら、トップページにはこれらの「強み」のかけらさえも見当たらず(アピールできておらず)、初めて来店(アクセス)されたお客様には、どんな特徴のお店なのか? 何が「強み」なのか? がすぐには伝わらず、実にもったいない限りです! 事実、私もお電話で直接お話をお聞きするまで、「小規模農園」の豆だけをシーズン毎にセレクトして販売していることなどまったくわかりませんでした。 現状では、新規客の方にはよほど時間に余裕があって、積極的に新しいコーヒーや新しいお店を探している方以外は食いつきにくい(新規客を捕まえる確率が低い)サイトだと思います。 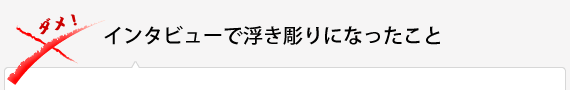 社長さんとネットショップの担当者である川井田さんにお電話でお話をお伺いしました。上でも述べましたように、ヴォアラさんは小規模農園さんの豆に特化して毎シーズン、それぞれの産地のいろいろな農園の異なった豆を販売されているとのことで、ずっと定番の物というのは基本的にはないそうです。←これは意外でしたし、特にどこにも記されていないので気づきませんでした。 その年、そのシーズン毎に、良い物をセレクトしている、いわばコーヒー豆のセレクトショップのようなお店のようです。 また、コーヒー専門店にはよくある、焙煎度合(豆を炒る深さ)は選べませんが、その豆の特徴とその日の気温や湿度などに合った最適な焙煎をヴォアラさんが見極めて行っているとのことです。 現状のネットショップの売上は、ほとんど、鹿児島の自社店舗や、ヴォアラさんの豆を使った東京にあるカフェなどで知った「実店舗」でのお客様を主とするリピーターさんたちがメインで、注文件数や売上は月間600件~700件、月商400~500万円(社長に掲載許可頂きました)と、実績はなかなかのものです。商品の良さを物語っていると思います! ただ、リピーター相手の現状からは、今のサイトの情報量やコンテンツでも十分かも知れませんが、今後、より売り上げを伸ばしていくには新規客の獲得もやっていきたいし、それが大きな課題ですね。 ヴォアラ珈琲について この1行だけでも、新規のお客様に一瞬で「この店の目利きは間違いないだろう!」と思わせられる「強み」なので、電話インタビューの際にも「ぜひトップページや看板にアピールすべきです!」と申し上げたのですが… 九州男児、薩摩隼人!? の実直で控え目な気質からか!? 自らの意思で時間と交通費なりガソリン代なりをかけて実店舗まで足を運んでくれて、説明や香りを感じたり、試飲もできる実店舗のお客様とは明らかにテンションが違うのです。 「なんだかよくわからない」と思われたら、クリック一つで即、お店を出て行かれるのです。 また、社長は現在、「定期通販」=定期的にコーヒーが届く売り方を実現しようと努力されているとのことで、これも商品の良さ&自信に裏付けられたリピーター対策になると思いますが、新規獲得策ではありません。 一方で、広告費はかけない会社方針であったり、コーヒー豆の内容量は250gと1Kgしかなく、お試しセットですら容量が大きい! 「お試し」といっても新規客にとっては量が多く、好みに合わなければ無理して飲み切るか、処分するか。いずれにせよ「満足度」ではなく「不満足度」になってしまいます。 また、プロにとっては今更ながらなのかも知れませんが、一般論、常識レベルのコーヒーの知識や情報、ウンチクといったコンテンツもありません。 とにかく「新規客」に対する戦略、商品、コンテンツがほとんどないのです。 ご本人によるとネットショップの担当者になった理由は、川井田さんの前職がデザイン系のお仕事で、PhotoShopやIllustratorといったグラフィックソフトが使え、画像加工やバナー制作、ページ更新ができるスキルをお持ちだったから、ネット担当者に任命されたとのことでした。 現在は実店舗の接客や店舗管理などの合間に、お店の片隅で商品登録や撮影、画像加工やページ制作を行っていらっしゃるとのこと。 受注対応や梱包出荷などの通販業務面は、川井田さんの居るお店とは別の本店のスタッフが行い、商品企画は社長や川井田さんを含めた他店の店長たちと相談しながら決めていくとのこと。 実際、バナー画像やページデザインのクオリティは十分に高く、デザイン制作担当者としては適任者だと思いますが、ネットマーケティングや通販業などは正直ご本人もよくわからず不安だし、実店舗の仕事のかたわらで週末など実店舗が混む日には手を付けられないとか、悩んだ時にネットショップのことをわかってくれる相談相手がいないなど、孤独感もあるように感じました。 これは川井田さんに限らず、企業でのネットショップの担当者にありがちな状況で、経営者が注意を払わなければならない点ですし、担当者も積極的かつ頻繁に経営者と情報共有、報・連・相して行く必要があります。 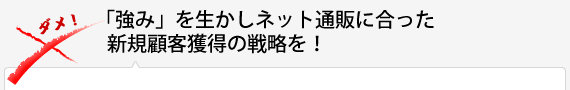 私はヴォアラさんのコーヒーを買って飲んだわけではないのですが、リピーターの多さ、売上、鹿児島の商圏規模で実店舗、しかもカフェのない豆販売だけのお店を4店舗も経営という実績から、その商品の品質、味の良さがうかがい知れます。 実店舗では好きなだけいくらでも試飲できるそうなのですが、ネットショップにおいても新規顧客に「まずはお試し」のハードルを下げ、買いやすく、いろいろな種類の豆を試してもらってお好みに合う豆を見つけてもらうような戦略、戦術が必要だと思います。 お電話でいろいろお聞きした中で、こんなアイデアが出てきました。 現状はバッグ詰めは業者さんに一括で依頼しており、豆の種類を選んだりはできないようなのですが… そこで「今販売中のコーヒーを全種類このドリップバッグで用意できれば、一度に10種類~20種類でもいろいろな種類のコーヒーをお試し購入していただけますね!」とご提案。 お一人のお客様、カップルやご夫婦のお客様、ご家族のお客様あたりを想定し… テイスティングシートには品評会審査員である社長のノウハウを込めつつも、素人や初心者でも簡単に記録できるような工夫を入れたシートが作れれば、お客様にとってはいろいろ飲んでみては評価記入していくことがヴォアラコーヒーの楽しみの一つにもなると思います。 ヴォアラさんに限らず、お茶やお酒などのお店でも、種類が多い商品ジャンルのお店では、お客様の「あれこれいろいろと試してみたい願望」は強いものです。 実店舗では試飲や試食で数種類は試せますが、意外にもネットショップでそれを行っている店はあまり多くありません。特にお酒は酒税法の縛りで小売店が勝手に瓶を開け少量ずつ小売りすることができないのですが… 商品とその味に自信のあるヴォアラさんならなおさら、とにかくまずは安くて手軽に多くを試せる「お試しセット」を手がけるべきだと思います。 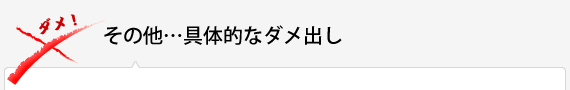 ヴォアラ珈琲について 上記2つのページに分かれているのですが、 井上社長や川井田さんが、初めて実際にお会いする方に最初の1分でヴォアラの自己紹介をするとしたら、何をどんな風にお話しされていますか? A4用紙1ページのパンフレットに収まるくらいのボリュームで、簡潔に短時間で伝わるように考えてみてください。 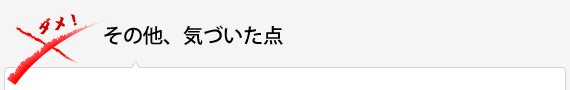 ●ニカラグア、ホンジュラス、エルサルバドル、コロンビア、メキシコ、ケニア…など産地がさまざまですが、文字だけでなく国が違うことをわからせるために、すべてのサムネイルメイン画像に国旗を入れたり、大陸地図に☆を入れたりなどの工夫があれば、よりいろいろな国や産地の商品があることがひと目でわかりやすく印象付けられると思います。 ●数多くの生豆を販売されていることは、専門店の中でもアドバンテージがある点だと思いますが、 「焙煎についてのご質問は受け付けておりません」と一刀両断するような表現ではなく、「焙煎についての個別のご相談、ご質問はご対応できかねます。生豆は焙煎の経験がある方や、ご自身で焙煎を楽しみたい方、チャレンジしてみたい方へおすすめいたします」のような穏やかな表現にしたり、焙煎についての一般的な解説コンテンツを用意したり、焙煎に関する専門書を紹介したりされると良いかと思います。焙煎機に関しては、現在は数十万円する高額なものしかないので、数千円~数万円クラスの焙煎機や手段も紹介して選択肢を広げてあげると、楽しみたい方が増えると思います。  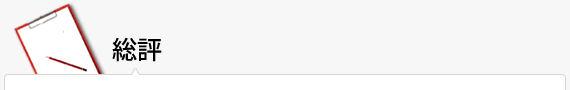 リピーターによる注文、売上実績は大したものだと思います! とにもかくにも、オンラインショップ=通信販売業であるということを改めて意識して、その上で新規のお客様をどう惹きつけるのか? どうすれば試してもらえるのか? どんな商品(豆の種類だけでなく、個別の量やパッケージ、組合せなど)が通販に適しているのか? 新規客獲得 → リピーター → ヘビーユーザー → 大ファン などなど、表面的な見た目やテクニック論よりも「通信販売業」としての成功モデル、勝ちパターンを作り上げていくことのほうが優先順位が高いと思います。 商品そのものやプロとしての専門性の深さ、レベルの高さは同業他社に比べても秀でたものがあると思います。通販業、特にネット通販業としての業態に合わせた体制や商品企画、マーケティング戦略を築いていければ、まだまだ大きく成長できるお店・企業だと思います。 担当者のスキルからネットショップは任せた、ではなくネット通販事業をどう育てていくか? ネット通販向きの商品はどんな構成にするか? という観点で、全社横断的なネットショップチームを築いていかれることをおすすめします。戦略立案に悩まれたら、いつでもお気軽にご相談ください! さて… オンラインショップの本質は表のホームページからだけでは見えない接客や、梱包、配送、そして商品そのもの等、「裏」の強みや弱み、そして個別の事情によるのが当たり前です。 実際に、「売れる・儲かる」という部分は、実はこの見えないところにこそ本質的な秘密や課題があるものです。 この「ダメ出し!道場」の企画は、公開という性質上、あくまで表から見たお店の印象や、そこから類推できる範囲の改善点をお客様目線でご指摘するものですので、ご理解ください。 |
このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。
今回はCSSではなく、テキストの文字組です。
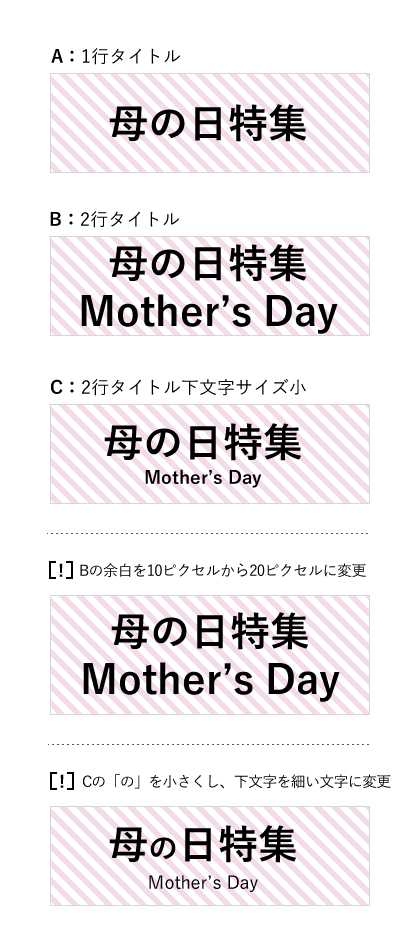 |
上記の画像を見てください。
上から、1行タイトル、2行タイトル、2行タイトルで下の文字を小さくすると3パターンの画像を作成しました。
この画像を見ていただければわかりますが、一番下の2行タイトルで下の文字を小さくするパターンが最も綺麗で分かりやすく見えます。
これが、バナーや写真に文字を入れる際のコツです。
大きなメインタイトルとサブタイトルの文字サイズを変更して作成することで、バランスのいい見やすい画像になります。
[ ! ] 余白について
文字サイズだけでなく、画像に枠がある場合、上下左右の余白も重要です。
上記Bの画像は、上下余白が10ピクセルですが、もう少し広い方が画像としては綺麗に見えます。
最下部に余白を20ピクセルにした画像を入れていますが見やすい印象です。
20ピクセル以上は余白を入れることを推奨します。
[ ! ] 文字のサイズ、太さについて
最下部の画像は、Cの画像「の」を小さくし、下部文字を細字にした画像です。
上下の文字により差がでますので、クオリティの高いバナー画像になります。
※単語内で「母の日」のように文字サイズの差をつけるのもポイントです。
2行文字で上下の大きさ、太さに差をつける。余白はしっかりと入れることがポイントです。
ご自身のショップ内のバナーや写真文字をこの機会に一度見直してみてください。
ぐっと印象が良くなるかもしれません。
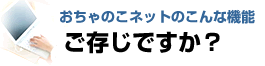 |
おちゃのこフォトについて |
|
このコーナーでは、おちゃのこネットの機能や提携サービスをご紹介していきます。
今回は、おちゃのこフォトについてです。
「おちゃのこフォト」は、iPhoneからおちゃのこネットに商品・コンテンツ写真を手軽にアップロードできる無料のアプリです。
近年のスマホ搭載カメラの性能向上に伴い、ネットショップの写真素材をデジカメではなくスマホで撮影することが多くなっています。
撮った写真をその場ですぐにショップにアップできることは、初心者ユーザーだけではなくリテラシーの高いベテランユーザーにとっても有用性の高いニーズです。
今回、おちゃのこネットとして初めてのスマホアプリをリリースするにあたり、機能を写真のアップロードに限定することで使いやすく実用的なアプリの提供に至りました。
今回搭載した機能は下記の通りです。
・スマホ内カメラロールの写真をおちゃのこネットサーバーにアップロード
・サーバー上にフォルダー作成
・アップロードした写真の移動・削除
このアプリの利用に追加費用は一切不要です。おちゃのこネットのアカウントさえお持ちであればどなたでもお使い頂けます。
おちゃのこフォトについて
https://www.ocnk.net/ocnk_photo/
プレスリリース
https://www.ocnk.net/pressrelease/index.php?id=15
マニュアル
http://www.ocnk.net/faq/index.php?action=artikel&cat=281635&id=1158
よろしくお願い致します。
FAQ(サポートくらぶ)
なお、お問い合わせは下記ページからお願い致します。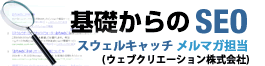 |
タイトルで上位表示を狙うコツ |
|
スウェルキャッチメルマガ担当(web creation株式会社)
おちゃのこ通信をご覧の皆様、こんにちは。
SEOサービス「スウェルキャッチ」担当のミスターSEOです。
今回は、EC通販サイトを運営する前に知っておくべき「タイトルで上位表示を狙うコツ」について説明させて頂きます。
■タイトルの扱い方を知る
ECサイトにおいて、成約率を上げることが収益を高める要素です。
しかし、商品を買ってもらうということは、自身のサイトにお客さんが来てくれなければなりませんし、その上で買い物をしてくれることが最低条件となります。
まず、大切なのが集客です。
買う買わないは一旦置いておきまして、ガラガラのお店とお客さんがたくさんいるお店では、後者の方が商品を買われる可能性は圧倒的に高まります。
ECサイトにおいても同じことがいえまして、アクセス数が一般のお店に例えると来店です。
なのでアクセス数を集めることに力を入れる必要があります。
その一つの要素としてあげられるのが「タイトル」です。
乱暴な言い方をしますと、コンテンツの内容よりもまずはタイトルに力を入れるべきで、魅力のあるタイトルは多くの集客を生み出します。
クリック率はもちろん、コンバーションにも大きな影響を与えるのが「タイトル」なので、軽々しく決めず、練りに練ったものを作り上げましょう。
タイトルには大きく分けると2通りの作り方があり、「検索クエリに関連させる」「ページ内容に関連させる」のいずれかで作ります。
検索クエリに関連させるタイトルは、ページのクリック率に影響するのに対して、ページ内容に関連するタイトルはコンバーション率に影響します。
かといってどちらか一つに重点を置くのではなく、両方を意識したタイトル作りが重要です。
なぜなら、クリック率が上がらないタイトルよりはたくさんのクリックが集まるタイトルが良いですし、ページの内容と一致しないタイトルよりも、ページ内容と一致するタイトルの方がユーザーにとって、そして検索エンジンにとっても望ましいからです。
では具体的に、どのようなことをタイトル作りに置いて意識すれば良いのか見ていきましょう。
■タイトル作りの心得
タイトル作りのポイントはまず、文字数です。
検索エンジンの状況によりけりですが、理想はおよそ全角28文字といわれています。
この文字数というのは、検索結果に表示されるタイトル文字数の制限を意味していて、制限を越えるとその先は「…」のように省略されてしまいます。
どれだけ素晴らしいタイトルでもユーザーに見えなければ、内容が伝わらなくなるので注意が必要です。
また、タイトルは限界いっぱいに長く作ります。
長ければ長いほど惹きつける単語を入れやすいですし、ユーザーに刺さるキーワードを入れやすいです。
限界いっぱいまでタイトル文字数を使うと、単調なタイトルではなく、ユーザーが良いと思えるようなものをつくれます。
次に、ユーザーにとってプラスとなる単語を含めるようにしましょう。
例えば「激安」「送料無料」「簡単」「たった~だけで」「本当は~」「図解」など、惹きつける単語を意識して組み入れていきます。
これがあるかないかだけで、ユーザーからの見え方は違います。
次に、キーワードや記号を使う方法です。
検索エンジンで何かを調べると、キーワード部分は太字で表示され、普通よりも目立った状態になります。
調べた単語が分かりやすく出ていると、ユーザーにとってもクリックする気になりますし、事実クリック率に大きな影響を与える一つの要素です。
どういうコンテンツなのかはご自身が一番理解していると思いますので、検索クエリを意識したタイトルを作りましょう。
また、タイトルには記号を使い、見やすくします。
【】、|、_、&などの記号を使い、注目させたい部分、強弱をつけたい部分に使ってみてください。
タイトル全体に締まりが生まれ、長々と書くよりもパッと内容が頭に入ってきます。
そして最後に、ユーザーが抱える問題に触れる点です。
例えば、「~が欲しい」「~を依頼したい」「~に困っている」という人が検索してくるわけですが、自分のコンテンツはどういう人に対して投げかけているのか明確にすると、タイトルの作り方にも影響してきます。
タイトルの魅力というのもやや曖昧な要素ではありますが、ご自身で検索エンジンを使っていると、どういうページが見たくなるのか分かると思います。
真似をするべきとは言いませんが、参考にして吸収するよう、意識してみてはいかがでしょうか。
★POINT
・タイトルに含めるべき要素を理解しよう
・検索クエリとページ内容に関連するタイトルを
スウェルキャッチでは、アクセス数・売り上げの向上に繋げることを第一にSEOに関わるアドバイスも行っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
【提供】web creation株式会社 SEOサービス「スウェルキャッチ」担当
|
激安SEOサービスのスウェルキャッチ
初期費用0円・月額費用980円からのSEOサービス:
SwellCatch(スウェルキャッチ)
編集後記
|
■おちゃのこネットのご利用方法については、おちゃのこサポートくらぶも参照ください。(http://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(http://www.ocnk.net/company/privacy.php) |
Copyright (C) 2004-2018 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.