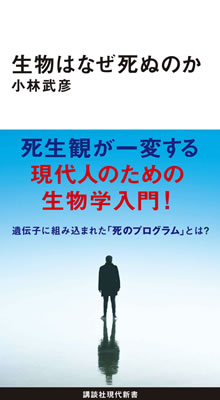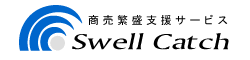「永遠の若さは不可能なのでしょうか号」 |
 |
「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。
オリンピックとお盆が終わったら、全国的に雨また雨。もう夏が終わってしまったのかと思いつつ、河川の増水や土砂災害が気になる日々が続いています。そして、コロナはデルタ株の猛威で医療崩壊の前に保健所が崩壊しそうです。
天変地異や感染症が恐ろしいのは、下手をすると命を失う危険があるからです。どんなに「人生100年時代」と言われても、事故や病気にはかないません。せっかくの命、少しでも長持ちさせたいですからね。
老いない、死なないという不老不死は、数千年にもわたる人類の大テーマです。しかし残念なことに、それをかなえた人はまだいません。アンチエイジング研究がどんなに盛んになっても、若返りや不死は不可能なのでしょうか。
その話題で議論するときには、「生命は必ず死ぬもの」という前提があります。しかし、本当にそうなのでしょうか。以前、盆栽園の取材をしたときに、そこの古老から「盆栽は根切りをするから寿命は永遠」という話を聞いたことがあります。根の先端にある成長点を切り落とすと、老化しないのだそうです。
盆栽でなくても、屋久島の縄文杉のように数千年の命を長らえている生命もあります。人間の寿命が数千年になったら、人生はどんなふうに変わっていくのでしょうか。
今回のオススメ参考書は、そんな生命と寿命の関係がよくわかる本をとりあげます。
おちゃのこ最新ニュース
|
今週のトピックス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お知らせ おちゃのこネットカート離脱フォローをリリース
|
ショップ売上の機会損失をAIが自動で解消
ネットショップではショッピングカートに入れた商品が決済されずに放置されることがよくあります。 |
オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!
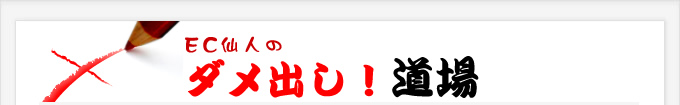
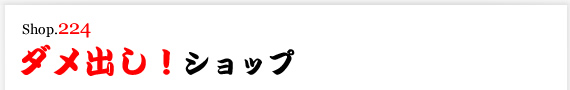
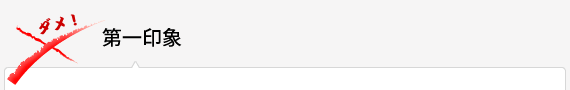 スマホサイトはレスポンシブ対応じゃなく、ガラケー版の古いタイプでテキストメニューだけで情報も少ないし、PCサイトもやや古めかしい印象。 ファッションやアクセサリー、食品など最新の流行や鮮度をウリにするタイプのお店ではないので、多少古めかしいデザインでも悪くはないですが… お店の特徴や、強み、キャッチコピーやお客様への姿勢(検索の方法案内やお問合せ大歓迎とか積極買取中!)などは、PCでもスマホサイトでもアピールすべきだと思います。 古き良きJAZZの名盤を扱う専門店であっても、ショップのインターフェースは必要最低限、今のスマホ時代に合ったものに対応して欲しいなぁ。
せっかく、スマホ対応機能のあるおちゃのこネットを使っているのなら尚更! もったいない! というのが第一印象です。 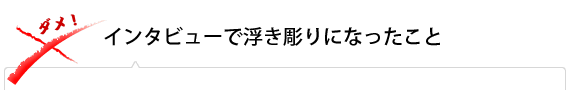 今回も、店主の河内さんにお電話でインタビューさせていただきました。ディスクノートはおちゃのこ店オープンが2008年。 店主の河内周二さんは御年75歳の大ベテラン。 今は仙台でディスクノートを経営されていますが、実は東京のご出身で、若いころは東京のレコード会社に勤め、仕事で各地を訪れる中、縁があって北海道は札幌にてレコード店を開業。 実店舗のほうもJAZZ、ROCK の洋楽輸入アナログレコードを中心にはされていますが、実店舗ではJPOP、CDも販売されています。 実店舗での品揃えは1万枚程度はあるようですが、おちゃのこ店では5000点までの出品制限を拡張して、現在約9000点程の商品登録があるようです。 新品もありますが、中古の一点物も多いので、SOLD OUTになっているものも多いですが、再入荷のリクエストもあるので、削除せず残しているそうです。 この辺りは中古品を扱う店として、「あるある」ですね。 現状(今まで)はとにかく、せっせと商品登録して、説明文を詳しく入力し、来店客が検索して見つけて買ってくれるのをひたすら待つスタイルですが、リピーターさん達からなかなか広がらず、新しい顧客を増やすことに悩んでおられるとのことでした。 SNSはFacebook、twitterを数年前に始めたが、なかなかネタも続かず、ここ2~3年は更新もできていないとのこと。 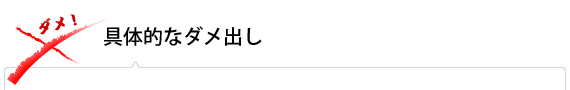 まずは、PC左メニューの「中古CD最新入荷はこちらから!」「中古LP最新入荷はこちらから!」などがリンク切れしているので修正しましょう。 ------------------------------ →具体的な方法は ぜひおちゃのこネットサポートにお問合せしてください。 ------------------------------ 例)たとえば JAZZの名曲に Take Five(テイクファイブ)という有名な曲がありますが…現状検索してみると… 「TAKE FIVE」か「take five」だと検索結果が11件。 理想としては、できればカタカナ、英語どちらでも検索ヒットするように商品説明文中にも両方記載してほしいですが… とはいえ、9000商品を更新、見直すのも時間がかかって大変だと思うので、とりあえずは「上手な検索の方法」例を検索窓の側に掲載して、お客様が工夫して検索してもらえるように仕向けていきましょう。 この場合だと、曲名やアーティスト名で検索する際は、できるだけ英語表記(半角)で検索すると最大数見つかります。 と明記しておくのが良いでしょう。 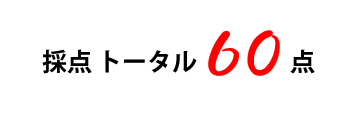 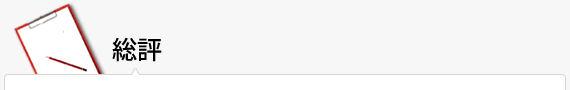 40年もの長きにわたってJAZZ、ROCKを中心にレコード店を経営されてきて、その知識や聞いてきた楽曲、アーティストの数はハンパない! と思います。 実店舗に伺って会話をすれば、その豊富な知識やご経験の中からいろいろなアーティストや楽曲のエピソードが聞けるでしょうし、趣味や好みを伝えれば、合いそうなアルバム盤を見繕ってオススメしてくださるでしょう。 ダウンロード系の音楽サイトやCD化されてない貴重なアナログLP盤などもいろいろ御存じでしょう。 また、データベース化されていない(ネットで検索しづらい)条件、 こういう少し変わった切り口での提案・オススメなどは、老舗店の店主ならではのノウハウを【強み】として活かしたセレクトができるのではないでしょうか? ------------------------------ それの JAZZアルバム盤 みたいなサービスが可能ではないでしょうか? お客様の好きな楽器、今まで聞いた好きなJAZZ アーチストや曲などを聞いて、好みに合いそうな物をセレクトして1万円~2万円で何枚かまとめてお届けするサービス。 できそうな気がします。 本家のいわた書店さんでは、単に好きな作家や書籍名を聞くだけでなく、「これまでの人生で嬉しかったこと、苦しかったこと」とか「何歳の時の自分が好きですか?」「いちばんしたいことは?」「あなたにとって幸福とは?」など、心や人生観に関するような質問もしながら本を選んでくださるようです。 参考)PRESIDENT Online の記事より 40年のご経験の中で、お店に来られるお客様達との会話で、そのお客様の好みやタイプ、考え方などをくみ取って、「それならこんなの合うんじゃない? これ聞いてみたら?」というやりとりはきっとたくさんあったかと思います。 そういうアナログなご経験こそ、ディスクノートさんの真の強みではないでしょうか。 「お問い合わせや相談も大歓迎!」とおっしゃる河内さんですから、お客様とコミュニケーションしながら好みに合いそうな盤を選んで「どうだー! このセレクトいいだろー!」とやりとりするのは、とかく、買い物カゴに入れられたものをただ梱包出荷するだけでドライになりがちなオンラインショップ運営も、きっと楽しみややりがいが生まれるのではないでしょうか? JAZZという音楽は昔からあって古いジャンルかもしれませんが、常に新しいJAZZとファンが生まれ続けているものなので… 若いJAZZビギナーがベテランJAZZ師匠からあれこれ教えてもらって古き良きを知りながら、自分のJAZZ お好みセレクトを作り出していくみたいなところがあると思うんです。 ただ9000枚の盤を陳列して待つだけでなく、ぜひ河内店長の頭と心の中にあるいろいろな切り口でのベストセレクションを、お店の新たな価値として提案・提供することで、新たなお客様がJAZZの名曲、名盤に出会える「セレンディピティ」(幸運なる偶然)をプロデュースなさってみてください! ──────── ──────── 今後の新しい戦略立案などお手伝いが必要な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。 以上、ダメ出し!道場 でした。 あとがき:今回の真夜中の原稿書きのBGMはJAZZ スタンダードの ────────────────────────────── 皆さん、コロナ騒動で大変な時期ですが、変革のチャンスでもあります! 差別化するアイデア出し、商品企画、ジリ貧回避、マンネリ化打破など、アイデアに行き詰まった際はぜひお気軽にご相談ください! ↓↓↓↓↓  毎回「ダメ出し!道場」登場のお店に電話でインタビューをさせていただいていますが、軽くインタビューと言いながら、実際には事前にお店のサイトを1~2時間かけてじっくり拝見し、お客様目線、プロ目線の両方から疑問点、気づいた点を洗い出してからお電話させていただいています。 最初はこちらからいろいろとご質問をさせていただき(インタビュー)ますが、後半はお店からのご質問、ご相談を受け、回答やアドバイス、アイデア、事例紹介など(プチコンサルティング)させていただいています。過去平均すると1店舗様に1時間半~2時間程度はかけています。 そのためか、インタビューさせていただいたお店の方々からは、下記のような感謝や喜びのお言葉を多くいただいています! ◆「目からウロコが落ちた! たくさん気づきがあった!」 ◆「自身が気づいていなかった強みや特徴を見つけてもらった!」 ◆「ただのインタビューかと思ったら、こんなにヒントやアドバイスを貰えるなんて思わなかった! ありがとうございました!」 ◆「新商品のアイデアまで出してもらえるとは! ワクワクしました!」 ◆「課題がハッキリと浮き彫りになり、やるべきことが整理できた!」 ◆「問題はホームページだけじゃないってことが、嫌というほどわかった!」 そこで、「ダメ出し!道場」に登場するのはちょっと勇気がないけれど、太田の電話インタビュー&プチコンサル は受けてみたい! というお店のために、有償でお受けしたいと思います! 通常 個別相談会:2万5000円のところ、メルマガ購読者限定で 先着順にて受付させていただきます。(週に2店舗程度・状況に応じて) 下記内容をご記入の上で太田まで直接メールください。 内容: さて… |
皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。
2021年のデザイン道場も半分が終わりました。
今回は、この半年のデザイン道場を振り返ります。
下記の一覧ページに全デザイン道場へのリンクがございます。
No.281~が2021年のデザイン道場です。
どんなサイトでも活用できますので、是非ご覧になってください。
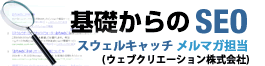 |
アクセス解析の基本 |
|
スウェルキャッチメルマガ担当(web creation株式会社)
おちゃのこ通信をご覧の皆様、こんにちは。
SEOサービス「スウェルキャッチ」担当のミスターSEOです。
今回は、EC通販サイトを運営する前に知っておくべき「アクセス解析の基本」について説明させて頂きます。
■アクセス解析でサイトを上手に運営
ECサイトのようにネットビジネスをしていくことにおいて、アクセス解析は運営のために欠かせない作業といえます。
アクセス解析は、運営するウェブサイトがどのような状況なのか、そしてどう改善すればさらに良い方向に向かうのかなど、大切なことが見えてきます。
具体的に何を把握することができるのかということについて、まずはサイトにアクセスしてくれているユーザーのことがわかります。
年齢や性別のほか、どこに住んでいてどういったジャンルに興味があるのか、細かいことではアクセスしているデバイスや時間帯といったことなども確認できるのです。
そのようなユーザーの情報を知って何の意味がある?と思う方もいるかもしれませんが、その後のサイトの運営において役立ちます。
ユーザーの年齢や性別がわかれば、どの年代や性別に興味を持ってもらえているのか知ることができ、その年代や性別が好きそうな商品の取り扱いを増やしたり、記事を量産したりすることができます。
アクセスする時間帯も、どの時間帯に記事をアップロードすれば良いのかなどの参考になりますし、どのデバイスからアクセスされているかわかれば、そのデバイス向けのサイトデザインを意識して改善することも可能です。
ユーザーの情報を得ることにおいて、あまり意味があるように思えない方もいるもしれませんが、これらのようにその後
のサイトの運営に役立てる重要な情報にもなり得るため、アクセス解析は積極的にするべきことなのです。
■ユーザーの行動を把握する
アクセス解析はユーザーの行動を得ることでサイトの運営に役立てられます。
具体的な例としては、流入経路です。
自身のサイトにたどり着くまでどのような経緯をたどったのかを調べることができます。
どこかのリンクや広告を踏んでアクセスしてきたのかということを知ったり、滞在時間などもわかります。
また、記事ごとのパフォーマンスも調べることが可能で、直帰率を調べたり、成約率の高い記事を特定したりすることも可能です。
直帰率が高い記事は、ユーザーが途中で飽きてしまったり、無益と感じて離脱してしまっていたりする可能性がありますので、一言でいうと直帰率の高い記事は改善の余地があるということになります。
対してコンバーション率が高い記事は成約率が高いということになりますので、記事としては良い働きをしていることになります。
このように収益に結びついているのかそうではないのかということを判断するためにもアクセス解析が必要ということです。
■アクセス解析は面倒臭がらない
アクセス解析と聞くと「面倒」な印象を受けるかもしれません。
とはいえ楽しかったり、楽にできたりする作業ではないともいえるでしょう。
しかしアクセス解析を軽視し、自分の思うがままにサイトの運営を続けていると「なぜアクセスが伸びないのか、収益が伸びない原因はなにか」ということをわからないままでいることになります。
アクセス解析で答えそのものを得ることはできないかもしれませんが、これからサイトをどういう風に運営していけば良いかというヒントをもらえるものなのです。
また、アクセス解析はサイトが適切に稼働しているかを把握するのにも有効です。
例えばシステムエラーが起こっているなどの何かしらのトラブルが起こっていた場合、アクセス解析をすることでそのトラブルに気づくことができます。
また、解析をするとして、改善の前後で情報を比較することも大切です。
自分の対処でどのような結果に変わったのかということをデータで確認することにより、アクセス解析をした意味があったかどうかがわかります。
対策して効果がない場合、やり方を変更したり、次なる課題を見つけて対処したりすることができるので、得られる情報は全てまとめておくことをおすすめします。
★POINT
・アクセス解析で今後の運営の方針を決める
・アクセス解析をしないと問題点も改善点も発見できない
スウェルキャッチでは、アクセス数・売り上げの向上に繋げることを第一に
SEOに関わるアドバイスも行っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
【提供】web creation株式会社 SEOサービス「スウェルキャッチ」担当
|
激安SEOサービスのスウェルキャッチ
初期費用0円・月額費用980円からのSEOサービス:
SwellCatch(スウェルキャッチ)
編集後記
|
■おちゃのこネットのご利用方法については、よくあるご質問も参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |
Copyright (C) 2004-2021 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.