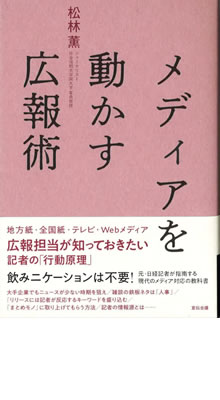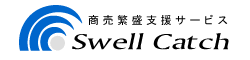「情報を上手に発信する方法は?号」 |
 |
「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。
客観的に、冷静に見れば1年間でなかなかの業績を残した管首相ですが、情報発信のまずさが致命傷となって、宰相の座を追われることとなってしまいました。まだまだやり残したことがあるはずですので、さぞや心残りなことでしょう。
そのことを見ても痛感するのは、適切なタイミングで必要な情報を発信することの重要性とむずかしさです。それが自身でできていれば、あるいは有能な広報担当者がいれば、今のように自民党総裁選が混沌とすることはなかったと思われます。
大企業ですら、不祥事が起きたときなどに対応が後手に回り、バッシングに遭うことが珍しくない昨今、私たちのような中小零細企業や個人企業では、日ごろから情報発信の体制を整えておかないと、企業活動の足を引っ張られてしまいかねません。
お金をかけずに多数の人たちに情報を届ける方法として以前から知られている方法は、マスメディアを利用することです。私などはマスコミ人の端くれとして、若い頃から企業経営者にプレスリリースの書き方をレクチャーしてきました。
プレスリリースで大事なのは、どのように書くか以前に「マスコミ関係者の気持ちを知る」ことです。相手が興味を持ち、掲載したくなるような情報発信の仕方を心がけないと、伝わるべきものもうまく伝わりません。
今回のオススメ参考書では、そのあたりのコツがよくわかる本をとりあげます。おちゃのこ最新ニュース
|
今週のトピックス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お知らせ おちゃのこネットカート離脱フォロー
|
ショップ売上の機会損失をAIが自動で解消
ネットショップではショッピングカートに入れた商品が決済されずに放置されることがよくあります。 |
オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!
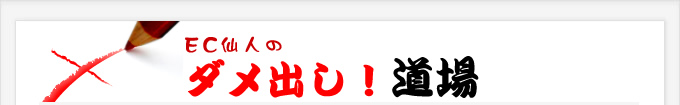
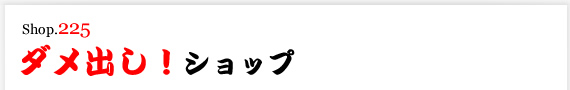
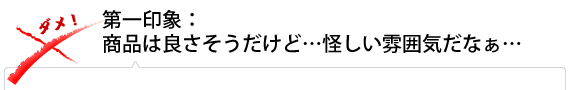 ちょっと派手目な蛍光色グリーンと赤やピンクやオレンジと、ビビッドな色使いのデザインに、ドーンとセンターに謎の【安心、安全のゴールドシール認定】 「いや、そんな認定、聞いたことないし…」 少し下にスクロールすれば、商品の蒸留水器が一覧されているのはよいのですが、もう少し下まで見ると… 【★ペットショップから動物は買わないでください!】の文字と、ペット業界で暗躍する…云々の見出しのYoutube動画へのリンク… 「いや、蒸留水器とはまったく関係なくない?」 トップページを見まわしても、 硝酸態窒素が出たミネラルウォーター3本 下部にはモノクロで「いったいいつの時代の写真ですか?」というほど古そうな謎の外国人博士たちの写真と紹介文。 でも紹介文を読んでも、いったいどこの大学や研究機関のどんな権威がある博士たちなのかは書かれていない謎。 他の左メニューも ほとんどの情報に出典や科学的な根拠が示されていなかったり、 ストレートに言えば そもそも、当店はどんなお店? いったいどんな店主がやってる? など基本的なことがまったく語られていないし、見当たりません。 店長やお店にとっての「当たり前」は、お客さんにとっては決して「当たり前」ではないのです。 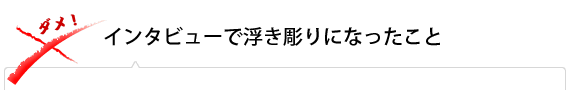 いつものようにお電話で店長の梅沢さんにインタビューさせていただきました。 それが約25年ほど前とのことなので、蒸留水器店としては大ベテランの老舗ネットショップですね。 長年、お水のことについて多くを学ばれてきたようで、お電話でも1つ質問をすれば、質問の答えだけでなく次々と話が広がっていろいろな知識や情報をお答えいただきました。 ただそれほど水に関して詳しくない私には、やや専門用語なども多く、ハードルが高かったり、話題の飛躍があちこちへ飛んで付いて行けないこともあったり(^^;) でも、とにかく、良いお水(蒸留水)についての熱い思いはガンガンに強く感じられました! サイト左メニューに「店長メッセージ」というページがありますが、 これは開店当初に書かれたもののようですが、ここを拝見しても店長の良いお水に関する出合いからWATER WISE社の蒸留水器、蒸留水についてに留まらず、途中からは 水やWATER WISE社とはまったく関係ないアメリカの通販サイト iHerbマーケットの話やハピタスというポイント還元サイトの話に展開したりと… とにかく明るく熱い梅沢店長さんでした。 あれも! これも! とご自身が良いと思うものをお伝えしたい! ただそのせいで、初見の私やお客様からすると いったん、外からの客観的な視点でサイトを見直してみる機会になればと思います。 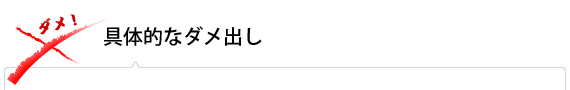 第一印象にも書きましたが、店長やお店にとっての「当たり前」はお客さんにとっては決して「当たり前」ではありません。 まずは初心に帰って、基本的なことから順を追ってお客様の関心事を理解していただけるような構成を考えていきましょう。 1)当店は何が強み・特長の何を主たるウリにするお店なのか? 2)そもそも蒸留水とはどんなお水なのか? 水道水や、ボトル入りウォーターとは何が違うのか? 一度沸かした湯冷まし水とは何が違うのか? 3)蒸留水器とはどんなモノなのか? 浄水器、整水器とは何が違うのか? 4)どんなラインアップがあるのか? 安い機種から高い機種まであるが、性能・仕様等はどこがどう違うのか? 5)ランニングコスト(電気代や水道代、消耗品費)はどのくらいかかるのか? 例えば4人家族の設定でシンプルに市販のペットボトル水やウォーターサーバーの月額費用などと比較など。製品寿命や買い替えの期間、1年あたり、1か月あたり、1日あたりのコストなどもできれば掲載 6)メンテナンス(掃除やフィルターの交換など)は面倒くさくないか? メンテを怠っても雑菌の繁殖などのリスクはないか? といった、興味を持ったお客様がアクセスしてきてまず気にするであろう点を順を追って整理して見てもらうようなサイト構成・客導線が必要だと思います。 ──────────── ・左メニューの「ゴールドシール」 ・蒸留水器各商品ページ 全般 また、各蒸留水器とも、蒸留水を作る能力について 蒸留水器の基本的な構成で、水道水を入れておく容器と、蒸留水が溜まる容器のそれぞれの材質や容量についての記載がありません。基本中の基本だと思うのですが。 下部に英語での仕様(SPECIFICATIONS)が掲載されていますが、そこにも書いてません。英語表記はちゃんと和訳した情報も掲載しておきましょう。輸入品の代理店として基本中の基本です。 電源は120VACとありますが、日本での100V電源でも十分な性能で動くのか? その辺の安心できる説明も、店長の言葉でちゃんと語って欲しいです。 ──────────── ・トップページ 下部の「★ペットショップから動物は買わないでください!」のコンテンツとYouTube動画リンク 店長の個人的な思いは理解できますし、個人的には私も賛同する内容ではあるのですが、蒸留水器の専門店としてトップページに掲載するような内容ではありません。お客様の関心も逸れてしまいます。 どうしても発信したい場合は、メルマガや店長日記、ブログ、SNSなどでお店のファンやリピーターの方にお伝えするようにしましょう。 ・左メニューの「iHerbのオススメ」は完全に外部サイト。しかも海外通販サイトへの外部リンクです。アフィリエイトなどあるのかも知れませんが、これも蒸留水器に興味を持ってくれたお客様にとっては気を散らす余計な情報ですし、外部への出口になってしまいます。 ・同様に左メニューの 「楽天のポイントが2重に」も外部の「ポイントサイト ハピタス」という外部リンクです。当店が運営しているわけでもないですし、蒸留水器とも無関係です。 ・左メニュー「博士たちの言葉」 とにかく無関係な外部リンクは せっかく来てくれたお客様の出口! になり得るものです。無駄な出口は無くしましょう。 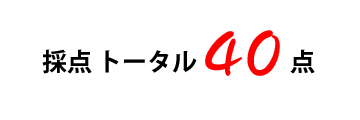 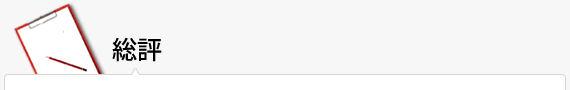 ひと言で言えば 結論は 電話インタビューでもおっしゃっていましたが、当店にアクセス来店されるお客様は既に水道水やペットボトル水に不安を感じておられる方が大半であるとのことですので、あえてそれらの水のリスクや配管の汚染などの情報を、イマイチ科学的根拠に欠けたり、そもそも信頼できるかどうかわからない外部サイトのリンクなどで掲載する必要はないと思います。 むしろ、そういうマイナスな情報を怪しい外部サイトのリンクで載せすぎることで、当店の信頼度が低くなり、「怪しさ」の印象ができてしまっているように思います。 それらの情報は削除して、純粋に、蒸留水や当店扱いの蒸留水器の信頼性や安心感を丁寧に説明するコンテンツを充実させていきましょう。 SEOやキーワードについてご質問がありましたが、今のままSEOで検索順位を上げて集客を増やしたところで、「怪しいサイトだなぁ」と感じたり、外部リンクでせっかくのアクセスも無駄になったり、悪い印象を広めることになってしまいます。 まずは来た方に安心、信用、信頼できるお店にしてからの集客です。 蒸留水、蒸留水器に集中して、正確な情報、アピールを充実させていきましょう。 またサイト歴が古いので、小さく荒い写真が多いですが、できるだけ高解像度で細部を撮った商品写真の充実や、動画の充実を心がけましょう。 最近流行の YouTuber がよくやっている 新製品の開封動画などもぜひ用意して、機種の開封、設置、稼働の様子などもぜひ見せて欲しいですし、蒸留水の良さや水道水・ボトル水との違いを示すような実験も欲しいですね・ 例)氷を作って 純度の違いで 氷の透明度や凍る時間が違うか? とか、 例)ガラスや車のボディに付けた水滴が渇くとき、水道水と蒸留水で水垢やミネラルなどが白く固まる様子が違うか? 例)塩や砂糖やお出汁や洗剤などが溶ける際の溶けやすさは違うか? 例)お肉や野菜や魚などを漬けておいた時の水の浸透度に差はあるか? などなど、水道水やペットボトル水と蒸留水の科学的・生物的な差を示すような比較実験などはぜひやって掲載して欲しいところです。 科学者でなくとも、誰でもできるような生活を前提とした身近な実験を見せれば、専門店として購入への説得力が増すと思います。 水分子のクラスターの大きさなどが本当に違うのであれば、溶解度や細胞への浸透度に差異が出るはずですので、説得力が高まります。 実際の商品や蒸留水を見たり飲んだり触ったりしたことはありませんが、なんとなく良さそうな商品であることは感じられますので、まずは怪しさを消し去り、説得力のあるコンテンツの充実で基本を押さえ、お客様により信用信頼していただけるようにしていけば、購入率はアップしていくこととと思います。 今後の新しい戦略立案などお手伝いが必要な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。 以上、「ダメ出し!道場」でした。 ────────────────────────────── 皆さん、コロナ騒動で大変な時期ですが、変革のチャンスでもあります! 差別化するアイデア出し、商品企画、ジリ貧回避、マンネリ化打破など、アイデアに行き詰まった際はぜひお気軽にご相談ください! ↓↓↓↓↓  毎回「ダメ出し!道場」登場のお店に電話でインタビューをさせていただいていますが、軽くインタビューと言いながら、実際には事前にお店のサイトを1~2時間かけてじっくり拝見し、お客様目線、プロ目線の両方から疑問点、気づいた点を洗い出してからお電話させていただいています。 最初はこちらからいろいろとご質問をさせていただき(インタビュー)ますが、後半はお店からのご質問、ご相談を受け、回答やアドバイス、アイデア、事例紹介など(プチコンサルティング)させていただいています。過去平均すると1店舗様に1時間半~2時間程度はかけています。 そのためか、インタビューさせていただいたお店の方々からは、下記のような感謝や喜びのお言葉を多くいただいています! ◆「目からウロコが落ちた! たくさん気づきがあった!」 ◆「自身が気づいていなかった強みや特徴を見つけてもらった!」 ◆「ただのインタビューかと思ったら、こんなにヒントやアドバイスを貰えるなんて思わなかった! ありがとうございました!」 ◆「新商品のアイデアまで出してもらえるとは! ワクワクしました!」 ◆「課題がハッキリと浮き彫りになり、やるべきことが整理できた!」 ◆「問題はホームページだけじゃないってことが、嫌というほどわかった!」 そこで、「ダメ出し!道場」に登場するのはちょっと勇気がないけれど、太田の電話インタビュー&プチコンサル は受けてみたい! というお店のために、有償でお受けしたいと思います! 通常 個別相談会:2万5000円のところ、メルマガ購読者限定で 先着順にて受付させていただきます。(週に2店舗程度・状況に応じて) 下記内容をご記入の上で太田まで直接メールください。 内容: さて… |
このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。
今回のデザイン道場は、画像をくり抜いた文字テキストを作成する方法をご紹介します。
背景画像を変更すると、色々なカラーやグラデーションのかかった文字を作成できます。
 |
配置/画像/コメント設定のフッター上部自由記入欄に下記のHTMLタグをコピーして貼り付けてください。
<h2 class="bgclip">BACKGROUND CLIP</h2>
デザイン管理→スタイルシートの編集から下記の指定をコピーして貼り付けてください。
※貼り付け位置は最下部にお願いします。
文字サイズは例として入れているだけです。必要なければ削除してください。
背景画像は変更してください。
h2.bgclip {
font-size: 80px;
background: blue url(https://cafe-responsive.ocnk.net/data/cafe-responsive/image/4774525_m.jpg);
background-clip: text;
-webkit-background-clip: text;
color: transparent;
}
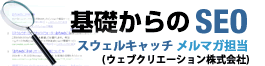 |
ユーザー目線にたった記事作成 |
|
スウェルキャッチメルマガ担当(web creation株式会社)
おちゃのこ通信をご覧の皆様、こんにちは。
SEOサービス「スウェルキャッチ」担当のミスターSEOです。
今回は、EC通販サイトを運営する前に知っておくべき「ユーザー目線にたった記事作成」について説明させて頂きます。
■購入者目線での記事作成を徹底
自分のECサイトで商品を買ってもらえるかどうかは、いかに商品紹介や宣伝を上手にするかというところが関わってきます。
商品説明を作成する時に大切なのは、購入者目線の内容にすることです。
売りたいという気持ちをあらわにした販売者目線の記事では、購入者にとって知りたい情報が不足していたり、セールス感が強まって敬遠されたりしてしまう可能性があります。
あくまで記事は「購入者目線」ということを前提に作成しましょう。
では具体的に、どのようにして購入者目線の商品説明を作成するのか、ポイントをいくつか説明していきます。
■6W2Hメソッドを意識
一般的な企業でも用いられることのあるメソッド、6W2Hを活用します。
語学では5W1Hの「what/when/where/who/why/how」はご存知の方がほとんどかと思います。
6W2Hはこれに以下を追加します。
・Whom (誰に)
・How Much(いくら)
としますと、6W2Hは全部で以下の通りになります。
・What(何を)
・When(いつ)
・Where(どこで)
・Who(誰が)
・Why(なぜ)
・Whom (誰に)
・How(どうやって)
・How Much(いくら)
記事作成の時にはこの6W2Hに条件を当てはめて準備することで、自分がいまどういった記事を書きたいのか明確になりますし、指針がずれません。
ではこれに化粧品のリップを商品例として売りたい条件を当てはめてみたいと思います。
・What(xxxメーカーのリップ)
・When(2ヶ月間の限定販売)
・Where(xxxで紹介されていた)
・Who(xxxメーカーや某xxxブランド)
・Why(色残りがよくフルーティな香りが人気)
・Whom (20代の女性におすすめ)
・How(宅急便でお届け)
・How Much(今なら送料無料のxxx円)
というように、作成する紹介記事の商品に当てはまる情報、運営者が何をターゲットにしているのかという情報を当てはめていきます。
中には当たり前とも言える情報が当てはまる部分もありますが、特に特徴的な条件ではない場合はそのままでも構いません。
大切なのは方針をブレさせないこと、記事の書き始めと終わりでずれたことを言わないようにすることで、それが売りたいターゲット層に対して魅力を感じてもらうのに重要なのです。
■メリット・デメリットは購入者目線で
販売者目線では、売りたい商品の特徴は出来る限り良い印象を持たせられるよう書きたいものです。
メリットは余すことなくアピールしますし、デメリットはデメリットと感じさせない書き方をしたくなるかと思います。
一見してそれが正しいセールスの方法に見えるかもしれませんが、実は何でもかんでも良いように書くと、それにより不信感を抱かれる場合があるのです。
例えば携帯用の水筒を宣伝するとします。
購入者目線で宣伝するなら、サイズを縦横奥行きで明記し、重さも記載しておくのが親切です。
さらに具体例として500mlのペットボトル1個分の重さなどを明記してあげると、ユーザーとしてはイメージしやすくなるので親切です。
そして例えば水筒の口径が狭くて洗いづらいなどが商品のデメリットとしてあるならば、口径を数値で記載するとともに、例えばスプレータイプの洗剤を使ったり、グラス用などの長めのスポンジで洗ったりすることをおすすめするように書いておくと良いでしょう。
デメリットをあえて書かないといったことをせず、こういうデメリットはあるけどどうすれば問題ない、その問題が解決できるのかという方法を提供してあげると、検討者は安心かつ信頼して購入するかどうか判断できるのです。
商品の良いところと悪いところ、そして価格に納得した場合に購入してもらうスタンスで良いかと思います。
なぜなら、その方がリピーターになってくれる可能性も高まりますし、レビューで高評価を得られる可能性も高まるはずです。
買ってから商品の悪いところを見つかるよりは、先に伝えておく方が良いということです。
商品紹介記事を作成する際にはぜひ、参考にされてみてはいかがでしょう。
★POINT
・6W2Hに条件を当てはめて記事を作成
・デメリットは解決策まで提供しよう
スウェルキャッチでは、アクセス数・売り上げの向上に繋げることを第一に
SEOに関わるアドバイスも行っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
【提供】web creation株式会社 SEOサービス「スウェルキャッチ」担当
|
激安SEOサービスのスウェルキャッチ
初期費用0円・月額費用980円からのSEOサービス:
SwellCatch(スウェルキャッチ)
編集後記
|
■おちゃのこネットのご利用方法については、よくあるご質問も参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |
Copyright (C) 2004-2021 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.